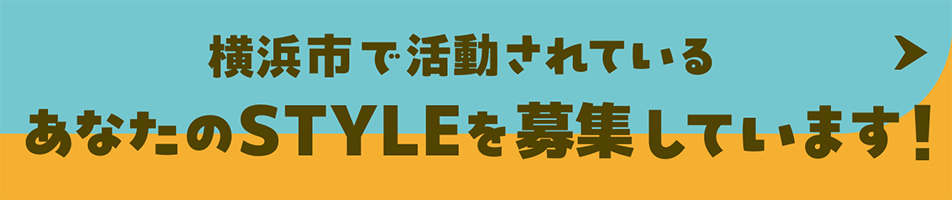ゴミ拾いを「遊び」に変えてみよう!
再使用エネルギー 生物多様性
この記事の目次
横浜駅西口の周辺エリアでは、「マグネットフィッシング」が試験的に行われています。マグネットフィッシングとは、ロープにつないだ強力な磁石で金属ゴミを“釣り上げる”新感覚のアクティビティのこと。横浜駅西口の水辺を楽しみながら、美しくしようというSTYLEです。もしかしたら宝物も釣れてしまうかも!?
河川は横浜駅西口の大切な資源。だからこそ、みんなで守りたい
横浜といえば海のイメージが強いですが、じつは市内には56本もの河川が流れています。横浜駅西口エリアもしかり。にぎやかな繁華街のすぐそばを、帷子川(かたびらがわ)と、その支流である新田間川(あらたまがわ)、幸川(さいわいがわ)が流れる“水辺のまち”です。川に囲まれたエリアには大きな商業施設や飲食店、オフィスに集合住宅など都市的な環境があり、このロケーションは全国的にもかなり珍しいそう。そんな貴重な環境の一方で、人の往来が多いがゆえに、ゴミの投棄や水質維持などの課題も少なくありません。そこで、横浜西口の活性化やプロモーション、環境美化などを行う、一般社団法人 横浜西口エリアマネジメントが中心となって、水辺を活かした独創的なアイデアが試験的に実施されています。これからご紹介する「マグネットフィッシング」は、そんなアイデアのひとつ。この活動を始めた経緯について、事務局長の籠田誠さんにお話を伺いました。

一般社団法人 横浜西口エリアマネジメント事務局長の籠田誠さん。
籠田さん:河川はまちにとって重要な資源です。水辺のまちだからこその取組でさらにまちの魅力を深めたいという想いとともに、大切な資源だからこそみんなで守りたいという気持ちがつねにあったんですね。そんな中、西区は2024年に区制80周年を迎えました。その節目に、地域の事業者や就業者の方々からワークショップ形式で「西口の水辺でやりたい80のコト」のアイデアを募ったんです。
「水辺でビールが飲めるお店をつくる」「水路を整備して交通手段として活用する」など、どのアイデアにも、もっと川に親しみ、この町を楽しみたいという前向きな視点が共通していました。そして「水辺でやりたいコト」が、川をきれいにするアクションとして発展していきました。
皆さんの環境意識の高さがあってこその展開だと籠田さんは続けます。

西口の繁華街を流れる新田間川。ペットボトルや食べ物の空き袋などが水面に目立ちます。
籠田さん:その一方で、この町にきてくれるたくさんの方にも、河川をきれいに維持しようとする意識の共有は大切だと感じています。マグネットフィッシングはそういう意味でもすごく有効なアクションだと思ったんです。
「アクティビティ×清掃」でゴミ拾いを“楽しく”
今回のマグネットフィッシングをはじめ、西口エリアの水辺の活動に長年寄り添ってきたKOKOPELLI+(ココペリプラス)代表の寺田浩之さんも、町の環境意識を高める活動についてこう話します。

“いつまでも人と自然がつながる社会”を理念に活動するKOKOPELLI+代表の寺田浩之さん。
寺田さん:都市部の河川の清掃はゴミの量が膨大で、ただつらい作業になってしまいがちです。そこで私たちはこの新田間川でも定期的にカヤックを漕ぎながらゴミを拾う「クリーンアップカヤック」を行なっています。“アクティビティ”と“清掃”を組み合わせることで、楽しみながらゴミ拾いに参加してもらおうというアクションなんです。
マグネットフィッシングも同様のコンセプトのもと、行われているといいます。
寺田さん:マグネットフィッシングはゴミを拾うのではなく「釣る」ことで、清掃がポジティブな活動に変化し、多くの方が参加したいと思ってくれるようになります。そして、町を訪れた人が、我々が楽しく活動する様子を目にすることで、川の美化に関心を持ってくれるようになる。そんな循環が生まれたら嬉しいですね。
KOKOPELLI+と横浜西口エリアマネジメントでは毎年帷子川をはじめとした周囲の河川の水質環境調査を実施しています。近年、川の表層部の調査ではCOD(水の中にどれくらいの有機物があるかを示す数値)が、清流と呼ばれる河川と引けを取らない結果がでていると言います。
寺田さん:西口エリアの河川は都市部にありながら、表層水を調べると水中の有機物を示すCODの数値が平均して4ppm程度であり清流と呼ばれる河川と同等であることがわかりました。
特に2019年では、同時期に行なった調査であの四万十川の河口部の数値と同等の数値を示しました。
だからこそ、ゴミが浮かんでいることで印象が悪くなることは、非常にもったいないことなのです。
“釣り”を楽しむ人の数だけ川がきれいになる
西口エリアのランドマークともいうべき、横浜VIVRE前の川に強力な磁石を投げ込み、川底に沈んでいる金属製のゴミを釣り上げる今回のマグネットフィッシング。今年3月に行われた第一回目ではなんと自転車を3台も釣り上げたそうです。
このアイデアを発案した、横浜駅西口商店会連合会、会長の宮田博幸さんはそのきっかけをこう話します。

横浜駅西口商店会連合会、会長の宮田博幸さん。
宮田さん:動画サイトでマグネットフィッシングの存在を知りました。ヨーロッパの河川に沈んだあらゆるものを釣りあげ、トレジャーハンターをしている映像でした。
その映像は清掃ではなかったそう。なぜ、川の清掃にマグネットフィッシングを取り入れようと思ったのか?の問いには「単純に釣りが好きだから」と宮田さんは笑います。

マグネットフィッシングに使われるネオジム磁石。通常の磁石の約10倍ほどの耐荷量があるものも。
宮田さん:「釣り」というキーワードがあると、ゴミ拾いでわくわくできると思ったんです。何が釣れるか分からない面白さがあるなと。

マグネットを受け取ったら、好きなポイントへ。思い思いに釣り糸(ロープ)をたらしていきます。

わずか1時間の活動で釣り上げた自転車はなんと5台。回収後は神奈川県 横浜川崎治水事務所が引き取り処理へ。

2回目の開催となったマグネットフィッシング。汗がしたたるような猛暑の中、およそ30人ほどの参加者がゴミを釣る体験を楽しみながらも真剣に取り組んでいました。道ゆく方々がいっしょになって川面を覗き込んだり、「なにをしているの?」と参加者との会話が生まれる場面も。楽しそうな雰囲気と珍しいアクティビティに周囲の関心も高まっていました。そんな普段目にすることも、体験することの少ない「釣る清掃」に参加した方の感想もさまざまです。

高校生のときから横浜西口エリアマネジメント主催のイベントなどに参加している松浦さん。この日の1号目となる自転車を釣り上げました。
松浦さん:ずいぶん昔から川底に沈んでいた自転車なんでしょうね。こんな大きなものが川に投棄されてしまう現実に改めて驚きました。重くて引き上げるのが大変でしたが、川の美化に貢献したという大きな手応えと達成感があります。

ダスキン品濃支店から参加の中島さん。
中島さん:実際にやってみると泥に深く沈んでいるので、空き缶ひとつ釣り上げるのもなかなか難しかったです。定期的にやれば、川底が確実にきれいになると思うので、また参加したいです。

飲み物の空き缶も多数。川のゴミの分析をしたところ、流れてくるのではなく、近隣で捨てられたものがほとんだとか。

ゴミを釣り上げて記念撮影。いい笑顔!

寺田さんが釣りあげたのはダンベルのウェイトでしょうか。
川底に沈んでいた自転車には、フジツボや水草がびっしりとくっつき、まるで別の生き物のような姿になっていました。空き缶にも泥が入り、ずっしりとした重みに。想像以上の重さに釣り上げる人からも「手伝って!」と自然と声が飛び交い、ちいさなチームプレーが生まれていました。
「楽しい」から清掃活動をみんなのものに。ゴミ拾いをもっと楽しもう!
ゴミ拾いというアクションを楽しみながら実践できるマグネットフィッシング。
楽しみながらゴミ拾いをする、そんな未来を目指して、プロジェクトは進展していきます。

みんなでいっしょに「とったぞー!」
横浜駅西口エリアで30年以上前からビジネスを続けてきたという宮田さん。日々の清掃は当然の活動としたうえで、改めてこんな思いを話してくれました。
宮田さん:私たちの清掃活動は、美化のためだけではなく、西口を訪れる人々の「意識を変えること」も目的です。多くの方に楽しそうと思ってもらえる方法で清掃活動を実施し、それを広く発信することで、より良い水辺の今日を実現できたらいいですね。

みなさん、マグネットフィッシング、お疲れさまでした!
あらためて、マグネットフィッシングは地域にある川という財産を知り、みんなできれいにしていく、そんな意識を市民の多くに伝えてくれる取組だと感じました。自転車のように悪意なしではそこにあるはずもないゴミが沈んでいることを知る。消えることない川底のゴミは人の手でしかきれいにすることができないと再認識すること。その上で、マグネットフィッシングのようにゴミ拾いを「遊び」に変えていくことは、ひとりひとりが楽しいからゴミを拾うアクションへと変化し、きれいな川の未来につながっていきます。
西口の川辺から、楽しさを力にした新しい循環にあなたも参加してみませんか。わくわくするコンテンツはいつでも開いていますよ。
【情報】
一般社団法人 横浜西口エリアマネジメント
https://yokohamanishiguchi.or.jp/
KOKOPELLI+(ココペリプラス)
https://kokopelliplus.wixsite.com/kokopelliplus