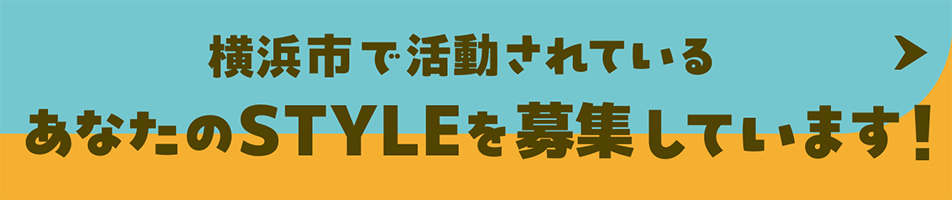大人の放課後にヨコハマの海を学ぼう
生物多様性
横浜の海に想いを寄せる人たちが集い、海について学び、触れ、体験する。そんな市民大学があることを知っていますか?これからご紹介するヨコハマ海洋市民大学は、海のことを正しく知る、大人のための学び場です。
大人が横浜の海について学ぶ市民大学
突然ですが、「横浜市にまつわる140km」と聞いて、何を思い浮かべますか?
じつは横浜市の海岸線の長さです。
では、この140kmの海岸線のうち、遊泳など一般市民が直接海にアプローチできる場所はどれくらいあるでしょうか。
答えは約2.5km。金沢区にある海の公園や野島海岸はその代表ですが、意外と少ないですよね。
横浜は「港のまち」ですが、市民が海で遊べる場所はごく限られています。しかし、国際的な港湾都市としての横浜の暮らしは、いつの時代も海とともに築かれてきました。
「ヨコハマ海洋市民大学」はそんな横浜の海について学び、もっと身近に感じてもらう場として2014年から始まった市民大学です。参加は誰でも可能で、象の鼻テラスを拠点に海洋研究の専門家などによる講座のほか、実際に海へ出かけてのアクティビティ体験など、年10回にわたり多彩なプログラムを開催。こうした活動は高く評価され、第29回横浜環境活動賞〈市民の部〉にて大賞も受賞しています。
今年で12年目を迎える同校の始まりついて、発起人であり実行委員長の金木伸浩さんにお聞きしました。
金木さん:もともと私は大さん橋の管理業務などを行う仕事をしていましたが、横浜開港150周年にあわせて、かつて港湾施設(港)だったエリアを市民に開放しようという横浜市のプロジェクトが動きはじめたんですね。そんな流れのなかで指定管理者として 、私も横浜の海や港と市民をつなげるというミッションを手がけることになりました。

ヨコハマ海洋市民大学実行委員長の金木伸浩さん。
以前は、横浜市民が身近に接することのできる海は少なかったと金木さん。
金木さん:かつてこのみなとみらいエリア一帯は*1保税倉庫があったり、一般の方が立ち入れない国や企業が所有する土地や施設が多く、市民が海に触れたり、くつろげるようなエリアではなかったんです。
横浜港と横浜市民の距離を劇的に縮めるきっかけとなったのが、開港150周年を機に掲げられた*2インナーハーバー整備構想です。これは、横浜ベイブリッジより内側のエリアを、市民に開かれた場所にしていこうという横浜市の整備計画です。
金木さん:横浜開港150周年を契機に、市民の憩いの場として象の鼻テラスとパークができ、港エリアが市民のために整備されたことは画期的なことでした。このエリアを当時責任者をしていた大さん橋をふくめ、もっと多くの市民に身近に感じてもらうにはどうすればいいのか?そんな問いからはじまり、たどり着いたのが、まずは横浜の海を知る“学びの場づくり”だったんですね。

毎月第一木曜の夜開講の講座。(不定期あり)毎回30〜40人ほどが参加するそう。年間400〜500名の延べ受講生です。
一般市民に開放されていく港や海をもっと身近に感じてほしい。そんなミッションからはじまったヨコハマ海洋市民大学ですが、立ち上げから関わる三上己紀さんは次のように語ります。

アドバイザーであり、再生可能エネルギーの講座も担当する三上己紀さん。長年ヨット乗りとして海に親しんできたそう。
三上さん:学びというと、どうしても課題解決の議論に終始しがちなのですが、私は学びの原点は「遊び」や「楽しい体験」にあると思っているんです。
いま、海で遊べる場所が減り、接点も少なくなっていると感じます。もちろん海には危険もありますが、海に行かなければ分からないことも多い。遊ぶこと、触れること、そして知ること、その体験の中に気づきや学びがあるというのが、ヨコハマ海洋市民大学の学びのコンセプトですね。
夜の港町を楽しんでもらおうと考案した企画、「汽笛が聞こえる港町のすてきなバーの大賞を決めよう!」はまだ実現できていないと三上さんは笑いますが、船をチャーターし、海上からレアな灯台を見にいくアクティビティや、大学の教授による海洋生物のマニアックな生態系の講義まで、開催する側も受講する人も楽しく学びに参加できる場が、横浜の港に誕生したのです。
子どもに伝えるため、まず大人から
ヨコハマ海洋市民大学で行われる講座は「うみをみる」「うみからみる」「うみのなかからみる」のいずれかに関連したものです。そして年間プログラムの最後には、ここで学習したことを活かした次のアクションを発表し、仲間と共有する場も設けられています。なお、これまでに受講した方は5000人を超えるとのこと。
ちなみに今年のテーマは「港」。講座の一部をご紹介すると、「出港!港まるごと講座〜学んで楽しむ横浜港」や「知られざる港インフラの舞台裏〜消波ブロックの役割と進化を学ぼう」など、アクティビティあり、マニアックすぎる講義内容ありと、興味深いものです。

「港ヌマにようこそ。」というタイトルが印象的。
港の奥深さを知り、港にハマろうがコンセプト。
講座内容は、これから改めて海について学ぼうとする大人を意識していると金木さんは語ります。
金木さん:海のことって日本の学校で深く教わることがあまりないですよね。そして大人になると自分から学ばない限り、知る機会も少ない。本来、海を知らなければ子どもに海に関する教育はできないはずです。それなのに、大人の経済活動によって生まれた様々な海洋環境の問題を、自分たちで解決することなく、子どもたちに引き継いでしまっている現状があります。だから、まずは海のことをよく知らない大人が勉強するきっかけになる場でありたいんです。それが講座をこれから海を学ぶ大人向けにした理由です。

受講生は30代から70代、職業もばらばらですが、海に興味があれば誰でもウェルカムという間口の広さも魅力のひとつです
全10回のうち8回参加すると、オリジナルの海洋認定書と「海洋教育デザイナー」の名刺が贈られます。でもそれは単なる記念品ではありません。ここで海を学んだ大人ひとりひとりが、*3インタープリターとなり、海を伝える人材として次のアクションへステップアップしてほしい。ヨコハマ海洋市民大学のそんな思いが込められています。

講座に8回参加すると贈呈される海洋教育デザイナーの肩書きが入った名刺。
金木さん:ヨコハマ海洋市民大学が目指しているのは、大人たちが、それぞれの視点で海のことを理解し、自分なりのアクションを起こす、そんな社会なんです。海のことを知ると海の見え方が変わります。例えば、海洋プラスチックの問題を理解している人なら、海でゴミを見つけたら当たり前のように拾い、他の誰かと共有する。海に関心を寄せ、行動できる人が増えれば、もう僕たちが市民大学をやる必要はなくなると思っています。

「海水と淡水の狭間〜海からの提案 ヨコハマの海でわくわくしよう」講師の石井彰さん。横浜市の環境創造、資源循環の分野に従事し、ダイバーとしても横浜の海の中を覗いてきた石井さん。市民科学という目線でヨコハマ海洋市民大学の運営を支えるおひとりで、実際の海中映像を織り交ぜた講座に会場中が見入っていました。

美しい横浜港の夜景を眺めながら海を学ぶ。
海が好きな仲間と出会う場所へ
海への好奇心をくすぐる入り口をつくり、次のアクションへの背中をそっと押すヨコハマ海洋市民大学。ここでの学びをきっかけに、魚を愛(め)で、魚食を推進する“さかなメデリスト”や、散歩道で拾うゴミをきっかけに海ゴミの課題に取り組む 団体を立ち上げた人などもいて、現在はプレイヤーとして横浜の海の未来を担って活動しています。そのきっかけのひとつはやはり講座での出会いのよう。

講座の受講をきっかけに「大岡川夢ロードデッキサポーターズ」という地域コミュニティの立ち上げに参加した新村さん。
新村さん:2015年に大岡川夢ロードデッキの清掃ボランティアチームを仲間と立ちあげ、清掃活動を開始しました。ここは有事の際、ゴムボートを停泊させる機能があるのですが、デッキにフジツボや牡蠣殻、藻などが付着してしまうと、ゴムボートが接岸時に破れてしまうことがあるんですね。そこで付着生物などを定期的に削ぎ落としたり、水上やデッキ上のゴミを拾う清掃活動を行い、町の防災機能を保っています。それぞれ別のチームや場所で清掃活動をしていた人たちがヨコハマ海洋市民大学でつながったことで実現した活動なのですが、これも海が好きだという共通の気持ちをもった人が集う同所ならではの広がりだと感じています。

大岡川夢ロードデッキに付着する貝類や藻の清掃はもちろん、SUPで水面に浮かぶゴミの清掃も。一回の活動でおよそ5kgほどのゴミを回収することもあるそう。
海の恩恵がなければ暮らしが成り立たない
頭では海の大切さを理解していても、積極的に関心を持ったり、海のことを改めて学ぼうとする人はまだ決して多くありません。
金木さん:「海を守りましょう」という言葉をメディアでよく耳にします。でも、海から守ってもらえなくなったら私たちは生きてはいけないんです。「海を守りましょう」という発想は人間の上からの目線です。海の恩恵なくして人の暮らしは成り立たないことを知る、そこがまず一歩目かなと思います。

横浜の海を知る、身近になる、好きになる。好きになると大切にしたくなる。そんな循環が続いていく未来へ
海水は水蒸気として空へ昇り、雨となって山々に降り注ぎます。山や森に降り注いだ雨はやがて水源林を抜け家庭に運ばれて私たちの飲み水に。食卓を彩る農産物も雨水なくして収穫はできません。海は人が生きていくためのすべての営みに欠かせない存在です。そんなシンプルなことに改めて気づくきっかけを、ヨコハマ海洋市民大学は遊びごころをたっぷりつめこんで、これからも伝えてくれます。

海のこと、港のこと。気になったらまずはヨコハマ海洋市民大学の扉を開いてみませんか?次のプレイヤーはあなたです。
*1 保税倉庫 通関手続きの終わっていない荷物を保管する倉庫
*2 インナーハーバー整備構想 開港150周年を契機に次の50年 (2059 年)を見据えた都心臨海部の理想の姿を描く構想(横浜市ホームページより)
*3インタープリター 自然や歴史・文化の魅力や価値を紹介し、地域と来訪者を結びつける役割のこと(日本インタープリテーション教会ホームページより)
【情報】
ヨコハマ海洋市民大学 https://yokohamakaiyouniv.wixsite.com/kaiyo
横浜環境活動賞
横浜環境活動賞は、地域で様々な環境活動を行っている皆様を表彰する制度です。
※ヨコハマ海洋市民大学は、第29回・市民の部「大賞」、大岡川夢ロードデッキサポーターズは、第27回・市民の部「実践賞」受賞者です。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/katsudosho/
【ヨコハマ海洋市民大学受賞一覧】
横浜環境活動賞 市民の部 大賞受賞
2022年6月 第29回 横浜環境活動賞(市民の部)大賞を受賞。
地域環境保全功労者表彰受賞(環境大臣)
2023年6月 環境大臣より地域環境保全功労者表彰を受賞。
第11回 横浜・人・まち・デザイン賞受賞
2024年3月 横浜市より「第11回 横浜・人・まち・デザイン賞(地域まちづくり部門)」を受賞。