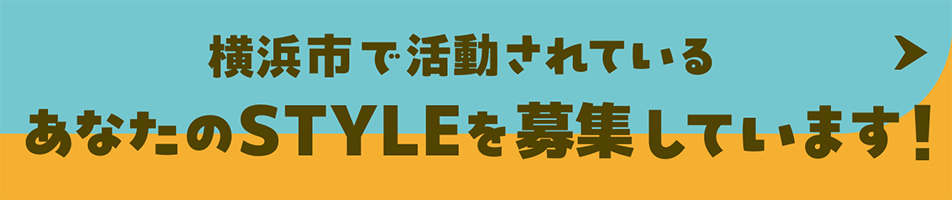おいしい地産地消を楽しもう
生物多様性
この記事の目次
横浜で長きにわたり地産地消に特化した活動を続けている、濱(はま)の料理人がいます。『TSUBAKI食堂』のオーナーシェフ、椿直樹さんです。
横浜には素晴らしい食材や、生産者が存在するにもかかわらず、その魅力はあまり知られていません。椿さんは、毎日の食卓に横浜産の食材が活用されるライフスタイルを提唱するとともに、「横浜の飲食店には横浜の野菜を使ってほしい」という想いを発信しています。
今回は、そんな椿さんの取組に迫ります。
都市と農業が共存、じつは食に恵まれている横浜
もしかしたら市内に住む人でも、横浜は農業が盛んだと聞くと驚くかもしれません。じつは横浜は、2003年(平成15年)に全国の市区町村で小松菜の生産量が日本一となったほか、キャベツやトマトの生産も盛んです。
参照:横浜市「グラフで見る横浜の農業」「横浜の野菜」
横浜のような大都市における農業、すなわち都市農業の魅力は、生産地と消費地が近いことにあります。新鮮でおいしい食材が手に入りやすく、輸送に伴う地球環境への負担も少なくて済むのです。また、都市農業の特徴として、消費者の細かなニーズに応える少量多品目生産の農家が多く、さまざまな種類の野菜が育てられています。
自宅の近くに直売所があって、朝採れの新鮮野菜が買える。横浜は、食の面でもとても恵まれた環境にあるのです。
その『横浜野菜』で地産地消を目指す洋食レストランを経営しているのが、シェフの椿直樹さん。横浜野菜の魅力や、日々の仕事、これまでの歩みについてお話を聞きました。

2020年にTSUBAKI食堂をオープンし、オーナーシェフを務める椿直樹さん。
椿さんは、以前から神奈川産の野菜のおいしさを知っていましたが、地元横浜にも数多くの生産者がいることがわかり、紹介された農家に足繁く通うようになったといいます。
椿さん:もともとは他のレストランで料理長として働いていたのですが、そのときに生産者のもとを何度も訪ねる機会がありました。そこで、生産者の方々の野菜作りに対するこだわりや情熱に触れ、「生産者をもっと多くの人に知ってもらいたい」という想いが芽生えました。同時に、一次産業の方と直接つながることの面白さに気づいたんです。
椿さんは、食を通じて生産者と消費者をつなぐため、生まれ育った横浜の野菜を広める活動を2003年から開始。地域の生産者とのつながりを深めます。そして2012年に「横浜野菜の料理を振る舞う店」として初めて自分のお店を開き、現在に至ります。

TSUBAKI食堂は馬車道駅より直結、横浜市役所の2階にあります。
活動を通じて、仲間が増えていった手応えと喜びについて、椿さんはこう続けます。
椿さん:一度つながりのできた農家の方が、トマトはこの彼のがおいしいよとか、この時期になったら誰々のレモンがいいとか、他の農家を積極的に紹介してくれたんです。親切心だけではなく、根底に「地域全体でおいしいものを作り、横浜の食を豊かにしたい」という共通の理念があるからだと感じました。個々の競争ではなく、「横浜の農業」という大きな枠組みで地産地消を盛り上げたいというマインドは、みんな同じなんですよ。

TSUBAKI食堂ではスタッフと一緒に、キッチンもホールも担当する椿さん。

店内には、TSUBAKI食堂の料理で使用している野菜の生産者の写真が掲示されています。
横浜野菜にかける想いを、生産者とシェフがともにする
椿さんが長年にわたって大切にしているのは、自ら農家のもとへ出向いて野菜を買い付けることです。この日は、横浜の地で13代にわたり農業を営む『苅部農園』の直売所『苅部FARM FRESCO』を訪れていました。

代表の苅部博之さんが運営する直売所は、開店前から行列ができていつもほぼ完売という人気ぶり。

年間で手がける野菜は100品目を超え、どれもその日に収穫したばかりの新鮮さが魅力です。
買い付けは不定期で、いろいろな農家の元へ行くという椿さん。自ら買い付けをするのには、素材や品質へのこだわり以上に、生産者とのつながりを大切にする気持ちがありました。

「苅部さんの野菜は形がきれい。袋詰めも本当に丁寧で、そういったものを使わせてもらっているという気持ちになります」と椿さん。
数多くの農家の中で、苅部さんは付き合いの長い一人。農業にかける熱意は大きく、同業者の中でも尊敬を集める存在だといいます。生産者とシェフ、立場は違っていても、横浜野菜を広めたいという想いが共通していた二人。椿さんにとって、苅部さんはどんな人かをお聞きしてみました。
椿さん:野菜作りの腕は言うまでもなく一流です。そして、横浜各所の農家をつなぐグループを作り、その中心でリーダーとして皆をまとめる存在でもある。志を同じくする仲間として、私は勝手に友人のように感じています。苅部さんが野菜で地域を盛り上げて、プライドを持って仕事をすることによって、横浜全体、あるいは関東や日本で、農家全体のレベルが上がっていくと思います。私自身、その姿に刺激を受けて、後から追いかけている感じですね。

この日の苅部さんのおすすめは、柔らかくて甘みのある間引きの白菜。
以前は、作った野菜を市場に出荷していたという苅部さん。現在は直売所で、対面販売を行っています。その中で感じた想いと、野菜作りで意識していることをお聞きしました。
苅部さん:購買につなげるには、おいしく作ることはもちろん、お客さんが「きっとおいしいに違いない」と思うものを作る必要があると感じました。都市農業の強みは鮮度の良さにあると思っています。私たちの直売所ではその日の朝採れの新鮮さにこだわり、お客さんの心を動かせるものを販売したいです。

苅部農園の13代目、代表の苅部博之さん。
都市農業ならではの特徴について、こんなことも教えてくれました。
苅部さん:広い農地では機械化がすごく進んでいますが、こういう都市部であればあるほど人力での作業が多いんですよ。例えば、うちは農地が15か所くらいに分散しているので、大きな機械ではなく鍬(くわ)を使った手作業をすることがよくあります。野菜の品種開発など新しいことにも挑戦しつつ、昔ながらの伝統的なやり方も大切にしていますね。
苅部さんによると、地産地消という言葉が広まったのは今から20年ほど前のこと。椿さんが活動を始めた15年ほど前から、徐々に認知されるようになったといいます。地産地消を発信し続ける椿さんは、苅部さんにとってどのような存在なのでしょうか。
苅部さん:椿さんは横浜野菜における地産地消のキーマンであり、先駆者ですよね。そして、野菜を使ってくれるだけではなく、私たち生産者の存在を引き立ててくれた方だと思っています。地産地消という言葉が浸透してきてから、都市農業の在り方は大きく変わりました。市場に卸して大産地の商品と競合するのではなく、地域のスーパーや直売所で販売できるようになったことはその一つです。色々な面で感謝の気持ちでいっぱいです。

野菜の新鮮さや、バラエティ豊かな少量多品目を強みとする都市農業は、地産地消と相性が良いのです。
ど根性サラダに18区丼、横浜の食を深めるさまざまなアイデア
買い付けた野菜は、TSUBAKI食堂で愛されるおいしい料理に。お店のメニューは横浜野菜を使ったお料理やドリンクなど、多彩なアイデアで溢れています。その根底にあるのは椿さん自身が生まれ育った地元・横浜愛に加えて、「土に根ざして生きる」ことを意味する“ど根性”という独自の価値観です。
看板商品の一つ『横浜名物!ど根性サラダ』は、まさに少量多品目で生産している横浜の農業を象徴するようなサラダ。見た目からみずみずしくハリのあるお野菜は、一口食べると、うまみがたっぷり詰まった緑の味の濃さに驚きます。シャキシャキとした歯ごたえや根菜や芋類の甘みから、土に根ざして生きることを味で実感できます。

おすすめはボリュームたっぷりのLサイズ、一人で全部食べる愛好家もいるのだとか。

『丸ごと茄子のミートグラタン』は茄子の元の形を生かして調理するので、椿さん自ら大きさや形を選んでいるそうです。
「横浜18区のメニューを作ってみるのはどうか」というお客さんの一言をヒントに、横浜18区それぞれのイメージを丼で表現した『18区丼』も名物の一つ。そして、18区内の学校と各区の食材を使って考案した『横浜食育18区丼』を展開するなど、お店を盛り上げるさまざまな企画からは、椿さんのアイデアマンな一面も見えてきました。
椿さん:子どもたちと一緒に食について考えたことは、とても刺激になりましたし、それが思い出になるなんて、すごく嬉しかったですね。「横浜に地場野菜や畑があるなんて知らなくて驚いた」なんて話を聞きながら、18か月やり切りました。

保土ケ谷区がテーマの18区丼では、区内の農家や小学生が育てた野菜がカラフルな温野菜丼になりました。
料理人として、地場野菜を使うことの魅力についてもお聞きしました。
椿さん:よく「おいしいね、どこの野菜なの?」と聞かれます。そんなとき、生産者の皆さんの想いをちゃんと背負っているのだなと、飲食店としてプライドを持てます。なんとなく仕事に来て、まかないを食べて休憩して帰るのではなく、「今日も一日伝えられたかな」と思えている自負があります。料理人としての自信にもつながりますね。

店内の『横浜地産地消百貨』で横浜の食を紹介したり、生産者とお客さまをつなぐニュースレター『よこはま村通信』を配布したりと、発信の多様さには目を見張ります。
横浜は地産地消の代表都市だ、と伝えることでひらく未来
横浜に農業のイメージをもっと根付かせたい、地産地消をもっと広めたい、という意欲から、最近とくに意識していることがあるといいます。
椿さん:法人のビジョンとして「横浜を地産地消の代表都市にする」と15年近く伝え続けてきましたが、昨年くらいからは「横浜は地産地消の代表都市だ」と言い切るようにしています。ちょっと伝え方を変えるだけで、「そうなの?」と気づく人がいるかもしれないと思ったからです。言葉一つでも人や社会が変わってくると期待を込めて、発信し続けたいですね。
おいしくて地球にもやさしい地産地消。まずは身近なスーパーの地場野菜コーナーや直売所、レストランなどで地元の野菜を味わい、その魅力に触れてみてはいかがでしょうか。「こんなに新鮮でおいしいんだ!」と体感することで一人一人の行動が変わり、やがてより良い未来につながるはずです。
【情報】
TSUBAKI食堂:https://tsubaki-shokudou.com/
苅部FARM FRESCO:https://fresco-karube.com/
取材させていただいたのは...
STYLE実践のヒント
「新鮮な地場野菜は、シンプルな調理法でもおいしく食べられます。私の著書『横浜の食卓 ~ど根性レシピ〜』では横浜野菜に興味を持ってほしいと思い、プロの味というよりも、ご家庭で誰でも楽しめるレシピをご紹介しています。これがきっかけで、地元の野菜を知り、料理って面白いねと思ってもらえるような内容を目指しました。いろいろな横浜野菜や農家の魅力を実際に楽しんでいただけたら嬉しいです」(椿直樹さん)
STYLE100編集部