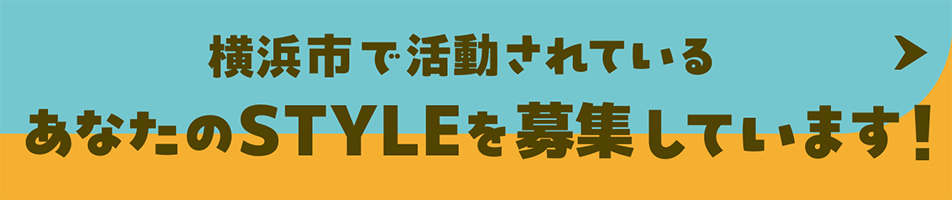地域に自然のあそび場をつくろう
生物多様性
この記事の目次
横浜市金沢区にある瀬ケ崎小学校の敷地内には、児童たちが日常的に自然とふれあうことのできる天然のフィールドが広がっています。都市化の波のなかで貴重な存在となったこの森は、幾度となく存亡の危機に直面しながら、様々な人々の協力によって保全されてきました。身近に自然のあそび場があることの素晴らしさと、それを維持していく活動の重要性とは。
貴重な森のあそび場を自分たちで守る
気候変動の影響は全地球的に広がっていますが、都市部に暮らす人々ほど、その実感にとぼしい傾向があります。都市では冷暖房やインフラの整備により気候の変化が生活に直接影響しにくく、異常気象も「一時的な出来事」として捉えられがちだからです。
こうした中で重要性を増すのが、子どもの頃から自然に触れ、四季や動植物の変化といった自然のサイクルの体験的な理解です。自然の“当たり前”を知っていなければ、その“異常”にも気づくことはできないはずです。持続可能な未来を築くための感受性や危機意識は、こうした幼少期の自然体験によって育まれるものだと思います。
これからご紹介するのは横浜市金沢区と横須賀市の境に位置する瀬ケ崎小学校。創立71年という歴史ある小学校ですが、じつは敷地内には自然豊かな森があり、それを開校から現在に至るまで大事に維持しています。
体育館裏に広がるその森は「アスレの森」と名付けられ、自然のあそび場として多くの子どもたちに親しまれてきました。在来・外来を問わず多様な植物や虫、動物が観察できる自然観察林であり、学校の授業でも、おがくずの中の幼虫を観察したり、森で集めた素材でものづくりを行ったり、森を整備したりなど、フィールドワークを通じた学びの場として活用されてきました。

竹や大きな木が気持ちのよい木陰をつくる森の中。大人が息切れしてしまうほどの急斜面を全速力で駆けめぐるこどもたち。

頂上には小学校周辺が見渡せる展望台も。数多くあったアスレチックなどの遊具は老朽化により撤去。自然のままの森が広がるアスレの森。
一方で、この場所は手つかずの自然であるがゆえに、台風による倒木で立ち入りが困難になったり、子どもの安全を考慮して山肌をコンクリートで固める計画が持ち上がったりと、これまで何度も存続の危機に直面してきたそうです。
瀬ケ崎小学校の大きな特徴は、児童、先生、そして地域の方々が一体となり、豊かな森を守り、維持するための活動を粘り強く続けてきた点にあります。

森のメンテナンスには地域の方々も協力しています。瀬ケ崎小学校の学区にお住まいであり、金沢区で酵素サロンを営む方が使用済みのヒノキのおがくずを定期的に提供。取材の日はこどもたち総出で森の斜面におがくずを撒きぬかるみなどをメンテナンス。撒いたあとは自然の急斜面滑り台ですべり放題!
昨年度からは当時の5年生が中心となり、「アスレの森再生プロジェクト」が始動しました。近隣の大学研究室や設計事務所などにも協力を仰ぎながら、この森をより地域に開かれた場所にするための取り組みを進めています。このプロジェクトに児童たちと共に参加し、地域を巻き込む大きな動きへと発展させたのが、瀬ケ崎小学校教諭の桐山智先生です。
現在6年生の担任として伴走する桐山先生は、このプロジェクトついてこう話します。

瀬ケ崎小学校教諭、桐山智先生。
桐山先生 毎年、*1総合的な学習の時間を使って1年間でどんな課題に取り組みたいかをこどもたちに聞くんですね。昨年度の5、6年生からでた課題がアスレの森をもっと地域に開いた場所にするためにどうしたらいいかでした。いろいろな話しあいの結果、アスレの森の前にみんなが集うことのできる「あすのこ広場」をつくろうという目標にたどり着いたんです。
では具体的にどんな広場にするのか。2014年からこどもたちとフィールドワークを実施している関東学院大学中津秀之先生の研究室の大学生、また、中区の株式会社櫻井淳計画工房さんに力添えをいただきながら模索していきました。「小さくロープで区切った空間でどんな遊びができるか考えよう」というワークショップでは保護者も交えてアイデアを出しあったそう。キャンプファイヤーや足湯、大人からは森でヨガやバーベキュー、妖精になれる場所というおもしろい意見も飛び出しました。
そんなワークショップや話しあいを経て見えてきたのは、アスレの森の入り口に小さなウッドデッキがたくさん並ぶ広場のイメージ。

関東学院大学中津研究室によるワークショップの様子。大学生と意見を交換しながら、ベンチづくりに挑戦する児童たち。

小さなウッドデッキとメインデッキをイメージしたあすのこ広場のイラスト。
アスレの森の自然を感じながら、みんなが自由にこのミニウッドデッキでやりたいことができる、そんな「あすのこ広場」をつくりたい。ミニウッドデッキ構想も動きはじめたアスレの森再生プロジェクトですが、櫻井淳計画工房の算出によるとミニウッドデッキの製作資金は50万円。この資金集めにクラウドファンディングにも挑戦。

campfireによるクラウドファンディング。挑戦中は、学校にホワイトボードを用意。支援が増えるたびこどもたちがその進捗をホワイトボードに書き込んでは支援の輪を可視化し、達成できるかへの不安は日に日に自信に変わっていったそう。

令和7年3月23日、24日にパシフィコ横浜にて開催されたサーキュラーエコノミーPlus×EXPO。初日トップバッターで活動報告をした瀬ケ崎小学校のみなさん。アスレの森のこれまでとこれからを発表しました。
クラウドファンディングの返礼品には、瀬ケ崎小学校のこどもたちが授業の中でさまざまな企業やまちのひとたちと協働し生まれた商品たちを採用。

クラウドファンディングの返礼品。横浜金澤黒船石鹸には給食で廃棄されるみかんの皮を再利用、太陽油脂株式会社に製造を受注。金澤八味唐辛子は*2 SDGs横浜金澤リビングラボと協働、唐辛子は瀬ケ崎学校の生徒が栽培しました。アスレの森のいちごいちえは、日本香堂株式会社に香りについて学びながらお香づくりをしたそう。
50万円を目標にスタートしたクラウドファンディングでしたが、学校への直接の寄付を加えると80万円という金額で達成。アスレの森や瀬ケ崎小学校のこどもたちを地域の財産として守る、そんな地域の方の想いがぐっと伝わってくるエピソードでした。
今年度になり、アスレの森プロジェクトは新6年生へと引き継がれました。アスレの森をもっと地域に開いた場所にし、10年、20年後、どう残すのか。小学生たちによるプロジェクトはさらにブラッシュアップをしながら瀬ケ崎小学校の探求は続いています。
クラウドファンディングやサスティナビリティに特化した商品の開発。こどもたちのアイデアや想いを真ん中に地域力を信じて進むだけ。
「アスレの森のプロジェクト」にとどまらず、多様なひとたちと地域課題を学びの種に変えてきた瀬ケ崎小学校。脈々とつづく地域の方々のアスレの森をこどもたちのために残したいという想いを根底に、そこからこどもたちの学びの場が広がっていったといいます。学校と地域で自然のあそび場を守っていく、さらには地域課題を取り入れ、ものづくりからもサーキュラーエコノミーやリサイクル、持続可能な環境づくりを学ぶ。地域とつながる学びについて桐山先生はこう話します。

こどもたちのフィールドでの気づきから課題やものづくりが生まれることもあると桐山先生。
桐山先生 実は、教員在職中に一年間横浜市から横浜市立大学に派遣された時期がありました。教員として学びを深めるという取り組みの一環です。当時、自分の中の学びのテーマが総合的な学習の時間の中で地域の人材と学校がどうやってつながっていくべきなのか、というものでした。研究する中で学校の先生と地域の方々にお互いの関わりについてのアンケートをとったのですが結果は興味深いもので。お互い邪魔をしてはいけないと思ってることがわかったんですね。企業の方も学校の勉強の邪魔をしてはいけない、学校側もお仕事の邪魔をしてはいけないと。
その遠慮を取り払うことで開けていく学びがあると桐山先生は続けます。
桐山先生 企業の方々がこどもたちに自分たちがもっている技術力や知識を伝えてくれる、それだけで素晴らしい学びです。研究室で学校と地域コミュニティについて学ぶうちにまずはこどもたちの好奇心ややってみたいを中心に考え、こどもに一番近い先生がアクションすることの大切さに気づいたんです。
アスレの森にある野苺を生かしたお香をつくりたいというこどもの声に、まずは日本香堂株式会社のお客様フォームから問い合わせてみたと桐山先生。
桐山先生「こどもたちがお香をつくりたいと言っているのですが」と問い合わせるとすぐに日本香堂さんからご連絡をいただいて。正直、こらちがびっくりです(笑)。その後、日本香堂さんの調香師の方が授業にきてくださり、アスレの森を生かした「アスレの森のいちごいちえ」が生まれました。

春めきはじめ、さまざまな命が誕生している森。「あそびも学びのフィールドとしても伸びしろはたくさんあります」と桐山先生。
桐山先生 こどもたちのやりたいという声に対して「無理」ではなく、まずは一緒にアクションしてみる。するとこどもたちは自然と地域の大人を信じてくれるというか、とくに瀬ケ崎小学校のこどもたちは地域の大人をすごく信じてると感じます。
例えば、道徳の授業の中で郷土愛や地域に対する愛好心を学ぶ項目はあり、そういった勉強も大事ですが、読み物的な教材として探求するだけではなくて、実際、地域の人と出会う中で、地域への郷土愛や地域に力を返していきたい、そういうリアルな学びを育てていきたいという思いはあります。土地に愛着がわくことで地域の課題に着目する。するとこどもたちがよりよい環境づくりについて調べはじめるんですね。結果、アスレの森のようにまちの自然が残っていくことにもつながっていくのではと感じています。
「学校は触媒」。こどもも大人も学校をハブにして、地域の循環を共に実現していくスタイルを。
アスレの森再生プロジェクト。瀬ケ崎小学校内の森の自然はそのままに、さらに森をまちにもこどもたちの学びにも生かしていく。そしてそれは森の存続にもなるという循環が生まれていました。
学校と多様な企業、人がつながって学びを実践していくスタイル、もっと広がっていくヒントはどこにあるのでしょうか?
桐山先生 まれに、自分のいる地域は学習の材が乏しいという先生にお会いすることもありますが、私はこどもたちと商品を作ったりする経験から地域の材はどこにでもあるという感覚になれたんですね。こどもたちが探究心を出してくることがチャンスでありはじまりです。金沢には*2 SDGs横浜金澤リビングラボという地域のハブ拠点もあり、そういった場所も活用してみると自ずと地域の課題や材、ステークホルダーは見つかると感じています。

どんな地域でも材はあり、これからの学びは地域と一緒に広がっていく。そんな未来はどんな光景が広がっているのでしょうか?
桐山先生 「学校は触媒である。」これは他校で校長先生をされていた方のことばですが、学校というフィルターを通すことで地域の方々のいろいろな力が見えてくる。学校はあくまで触媒でそこに地域の方の力が発揮されるとさらにお互いの学びが広がっていくという意味です。近年、学校の勉強の仕方も変わっていて、椅子に座ってノートをとる勉強のイメージからより深い学びができる環境へと変化しています。学校の外での学び、また学校の中にも入ってきてもらいたい。学校をハブにして地域の方に学校にきていただきながら自分たちのお仕事や特技をこどもたちに伝えてくださって、知識をいただいたり、こどもたちの活動を手伝っていただいたり。するとお互いの関係性も変わっていくチャンスにもなりますよね。地域コミュニティが豊かになる循環をつくっていけたらなと思います。

5年生から6年生になり今年1年間であすのこ広場を創出していくこどもたち。「みんなが自由に交流できる場所にしたい」「ウッドデッキで日光浴したい」「大人とのワークショップでもっといろんな意見を学びたい」こどもたちの声に楽しむことも忘れない頼もしさを感じました。
横浜市は世界でも指折りの大都市ですが、その郊外には今なお豊かな自然が息づいています。休日には、ぜひ木々や森で暮らす生物のさざめきに耳を澄まし、澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んでみてはどうでしょう。都市部の暮らしでは忘れがちな自然への畏敬や愛着がより深まるはずです。
*1 総合的な学習の時間 変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしていることから、これからの時代においてますます重要な役割を果たすものである。(文部科学省ホームページより)
*2 SDGs横浜金澤リビングラボ https://livinglabsupportoffice.yokohama/livinglab/kanazawa/