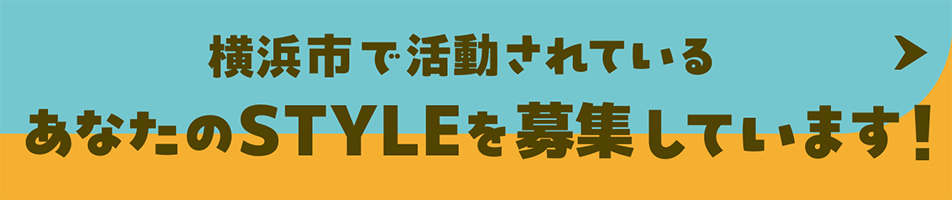地球にやさしいスポーツ大会に参加しよう
生物多様性

この記事の目次
45年前、山下公園前に広がる横浜港の水質改善を目指し、市民の有志による清掃がはじまりました。その長年の取り組みが実を結び、いまでは厳しい水質基準を満たす海として横浜港は『世界トライアスロン横浜大会』の開催地となっています。第15回の記念大会でもある2025年、豊かな自然と共存するトライアスロン大会は、都会の海でどのようにして実施されたのか?「つくる側」「ささえる側」それぞれの想いを、“海をまもるSTYLE”として取材しました。
横浜の海でトライアスロンを。描いた未来を叶え、今がある。
都会の海は汚い、そんなイメージを抱いている人は現在も多いのではないでしょうか。
山下公園前、日本郵船氷川丸が浮かぶ横浜港も、かつては高度成長期、人口増加の影響を受け水質が激変、汚濁してしまったという過去があります。

2008年頃の横浜・山下公園前の海。(提供:横浜市環境科学研究所より)
いま、その横浜港の海で世界トップレベルの選手が泳ぎ、競技する国際的なスポーツイベントが開催されているのをご存知ですか?
その大会とは『世界トライアスロン横浜大会(以下、横浜大会)』です。

トライアスロンは、豊かな自然環境の中、スイム(水泳)・バイク(自転車ロードレース)・ラン(長距離走)の3種類をこの順番で連続して行う競技です。2000年のシドニーオリンピックで正式なオリンピック競技になったこともあり、その競技人口は世界中で増えつづけています。
横浜で、トライアスロンの国際大会の計画がはじまったのは2007年。当時の海は、人間が泳ぐどころか、生き物が棲むことすら困難だったそう。開催が危ぶまれる中、下水道整備事業や水質浄化実験などハード面の整備からはじまり、また、横浜市の環境科学研究所も中心となりさまざまな方法で2年にわたり水質浄化に取り組みました。結果、水質が改善し、2009年にトライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会を初開催。2011年以降は継続的な開催へと発展していきました。

2日間に渡り開催された2025世界トライアスロン横浜大会。国内外のプロ、アマチュア選手が横浜の海とまちを駆けめぐりました。© Shugo TAKEMI/ Triathlon Japan Media
2012年にはこの大会において、イベントの持続可能性を高めるためのマネジメントシステムに関する国際規格である『ISO20121』を日本で初めて取得しました。ISO20121ではイベントの運営において「廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進」「地域社会との連携による社会的包摂の促進」「持続可能性を考慮した経済的意思決定」など、環境・社会・経済の3つの側面をバランスよく考慮することが求められます。
横浜大会では、大会運営に関わるすべての人々が協力して、これらの項目に対して尽力し持続可能なイベントづくりに取り組んできました。その努力が評価され、これらの国際的な認証や評価を受けることができたのです。
泳げる海をよみがえらせる!開港150周年に横浜でトライアスロンを。
横浜港の水質の改善という課題、そして、トライアスロンという豊かな自然環境なくしては成立しない競技を大都市横浜で開催したいという想い。決して平坦な道のりではなかったことは優に想像できますが、この両輪をうまくかみ合わせたことで、多様な生物が暮らす、豊かな海がよみがえりました。

約50名のこどもたちによるヒラメの稚魚放流セレモニー。元気に泳いでいく稚魚の姿に子どもたちの歓声が響きます。
2009年の第1回開催時から大会開催に深く関わってきた、世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会の大久保さんは初回開催を「感慨深くて涙しました」と振り返ります。

世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会事務総長 大久保挙志さん。
大久保さん:横浜開港150周年を記念して、「スポーツのビッグイベントとして横浜で国際的なトライアスロン大会を」、という構想がトライアスロン競技団体と横浜市の間で生まれました。トライアスロンは、水、緑、そして空気が澄み渡っているような、自然環境に恵まれた場所で行われる競技ということもあってか、集客のしやすさや認知度には課題を抱えていました。大都市横浜での開催は、多くの市民にトライアスロンを知ってもらえるとともに、横浜を世界に発信できる絶好の機会でもありました。競技と都市の発展、両方にメリットがあったのです。ただ、開催する上ではスイムの舞台となる横浜港の水質を改善しなければなりませんでした。そこでトライアスロンを契機として横浜の海を泳げる海にしていこうというビジョンが立ちあがったんです。開催基準をクリアするため、水質改善をしてきた2年間はそれは猛烈でした。でも、横浜市の各関係局が一丸となって取り組み、結果を出せた。これは紛れもなくきれいな海がよみがえったという瞬間でした。

山下公園から見下ろした透き通っている横浜港。
大都市横浜で大規模なトライアスロン大会を開催しつづけること、それは海の環境も守られていくことにつながっていると大久保さん。
大久保さん:横浜港は港湾区域なので遊泳はできませんが、現在泳ぐことのできる水質です。
大会を開催する上で、トライアスロンの国際団体はより厳しい水質基準を設けていますが、それもクリアしています。これからもこの海を見た人々が泳いでみたいなと思えるような水質にしていきたい、それがわれわれ事務局の思いです。
今日の稚魚放流も放流すると同時にきれいになった海を子どもたちに見てもらう。そこに意味があると思っています。トライアスロンを観戦するだけではなく、トライアスロンの大会がここで開催できるということは海がきれいだからだということをもっと知ってほしいです。
1時間に5トンのゴミ!?横浜出身のダイバーたちが取り組み続けた海底清掃。
15回記念大会の一環として、初めて行われた子どもたちによる*1ポンツーンからの稚魚の放流。その準備に奮闘し、45年にわたり海底清掃に携わってきたボランティア市民団体『海をつくる会』の事務局長、坂本さんも大会への想いをこう話します。
坂本さん:45年前の海底清掃では幅370メートル、沖に25メートルの海中にあるゴミを約300人のダイバーが潜り、陸へと運びました。1時間の清掃で5トンのゴミです。それが近年は100キログラムから200キログラムまでに減少しました。
大会があるたびに感じますが、世界の海を見ているプロの選手が横浜の海でレースを行い、この海はきれいだっていってくれた瞬間が一番感慨深いですね。
「横浜に長く暮らしている人ほど、横浜の海で泳げることを知って驚く。」と坂本さんは笑います。

*2海をつくる会事務局長・坂本昭夫さん。企業で海外赴任をしながらも地元の海をよみがえらせるため長年清掃に携わってきたそう。
坂本さん:確かに横浜港は汚濁してしまった過去もあります。でもこの大会をきっかけにこのきれいになった海を見てほしいです。そして、横浜の海は汚いという先入観を塗りかえてほしいなと思います。今日は、大会と同時開催のハマトラFESでこの横浜港に生息する魚の展示もしています。これだけの生命がここに暮らしている、生命が戻った海なんだということをしっかり見てほしい。そして、もっときれいな海をつくるためにできる新しいアクションをみんなで考えて、きれいな横浜港を持続させていけることを願っています。
本大会を地域と共に支える横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課の相田係長は大会を振り返りこう話します。

横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課 相田涼平係長
相田さん:子どもたちによる稚魚の放流は予想を上回る盛り上がりでとても嬉しく思いました。ISO20121を先進的に取得したことで、持続可能性に対する高い意識は早くから大会に根付いていたと思います。大会を通じたサステナブルな取り組みは、これまでにもたくさん行ってきています。昨年の大会から、大会で使われたペットボトルの*3水平リサイクルを開始し、さらに今大会では紙コップから紙製品へのリサイクルをスタートしました。今後とも地域をはじめとするたくさんの方と協力しながら、持続可能な大会を意欲的につくっていきたいです。
多くの人たちの情熱と信念、そしてあきらめずに行動しつづける力が、横浜の海をよみがえらせたのだと強く感じたお話でした。
世界中の選手も支持する、大都会横浜の美しい海を未来へ。
最後にお話を伺ったのは、本大会のアンバサダー、プロアスリートのおふたり、上田選手と宇田選手です。
海外の大会の経験も豊富なおふたりにとってあらためて横浜大会の魅力とはどんなものなのでしょうか。

ハマトラアスリートアンバサダー、オリンピアン・上田藍(リソル・稲毛インター/千葉)選手(左)と同じくアンバサダー、パラリンピアン・宇田秀生(NTT東日本・NTT西日本/滋賀)選手(右)。
上田さん:この横浜大会は観光地を巡るようなレースコースになっていて出場される方は口々、景色がすごくきれいだとおっしゃられます。その中でも、横浜港のシンボルとも言える氷川丸の横を泳ぐことに驚かれますね。氷川丸のように大きな船を海から見上げるなんてなかなかない経験ですよね。
世界的に見ても海という自然環境によりコミットした大会だと上田さんは続けます。
上田さん:この大会は海を豊かにする大切さを感じてもらえる取り組みを積極的に行っていて、環境を守り持続可能な大会として世界でも誇ることができる、それも魅力だと感じています。

同時開催のハマトラFES会場にて、海をつくる会による横浜港に生息する魚の展示。大会を開催するだけではなく、海や環境について触れ、知る場を作る「グリーントライアスロン」にも取り組んでいます。

環境に優しい植物由来の素材「ピエクレックス」で製作された完走賞のタオル。土に還る素材で、使用後は回収して堆肥化され、農業などで活用されるという循環型の取り組みが進められています。
宇田さん:横浜にはおいしいご飯屋さんがいっぱいあって、世界から集まる選手にも大人気なんです。競技が終わった後も、選手や応援してくれたひとみんなで、最後までこのまちを楽しめるところも魅力だと思います。
大都市、横浜での開催だからこそ多くの人に届くメッセージがある。実際、取材前日に開催されたパラトライアスロンのエリートの部でレースに出場した宇田さんはさらにこう続けます。
宇田さん:どんなスポーツも、生で見てもらえるとものすごく迫力が伝わると思うんですね。横浜大会は本当にたくさんの方が来てくれる大会です。僕自身、トライアスロンの迫力をたくさんの方に感じてもらえてると実感できるし、それがとても嬉しいです。その迫力に魅了される人が増えて、大会を重ねるたびに横浜の海はトライアスロンができるくらいきれいなんだという認識が広まり、水質がさらに良くなっていく循環が生まれるといいなと思います。これから何十年も続いていく大会であってほしいですね。

未来へつなぐ、きれいな海を。© Shugo TAKEMI/ Triathlon Japan Media
トライアスロンのような野外スポーツは、体を動かすだけでなく、自然と触れあうことで心も体もリフレッシュすることができます。でも、その舞台となる豊かな自然がなければ、スポーツの楽しさも続きません。横浜大会では、選手が泳ぐ海をきれいに保つために、多くの人が情熱をもって持続可能な海づくりへと努力を重ねていました。自然を大切にすることとスポーツの楽しさは、常に一緒なのかもしれません。これからも私たちや未来の子どもたちがスポーツを楽しめるよう、いまできることを考えてみませんか。
*1 ポンツーン 水に浮かべた桟橋のこと。トライアスロンでは、選手がスイムスタートの際に海に飛び込むための足場として使われる。
*2 海をつくる会 1981年横浜の観光名所山下公園前の海底清掃を機会に生まれたボランティア市民団体。
*3水平リサイクル 使用済み製品を資源化し、同じ製品を再生産、再利用すること
【情報】
2025世界トライアスロン横浜大会
https://yokohamatriathlon.jp/wts/index.html
宇田秀生選手(NTT東日本・NTT西日本/滋賀)
小学校からサッカーを始め、高校卒業まで県代表として活躍する。2013年、仕事中の事故により利き腕である右腕を切断。
半年後、リハビリの延長でトライアスロンを始める。2017年7月に世界ランキング1位。東京2020大会で念願のパラリンピック出場を果たし、日本パラトライアスロン史上初となる銀メダルを獲得。
上田藍選手(リソル・稲毛インター/千葉)
中学では競泳選手、高校では陸上選手として経験を積み、高校3年の夏にトライアスロンに初挑戦。7度の日本選手権優勝、アジア選手権では5度の優勝、オリンピックには3大会連続で出場(北京、ロンドン、リオデジャネイロ)。2016年には世界シリーズランキング3位となる。2022年シーズンからアイアンマンレースに転向している。
アイキャッチキャプション:© Shugo TAKEMI/ Triathlon Japan Media