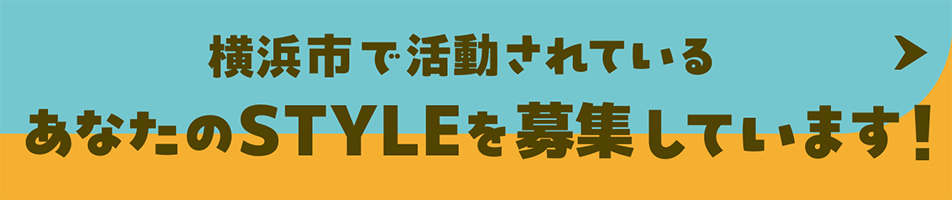自分たちの手で100年先まで水源を守ろう
再使用エネルギー 循環型経済 生物多様性
蛇口をひねると、いつでも良質な水が飲める横浜市の水道。
じつはその水源の1つは、山梨県道志村を流れる「道志川」であることを知っていますか? そして、横浜市はおよそ100年前から現在まで、この水源を守る取組を続けています。「自分たちの水源は自分たちの手で守る」。そんな想いのもと、水源を保全し、整備する取組が脈々と受けつがれています。横浜市、道志村、そして有志のボランティアたち(最高齢は89歳!)が手を取り合い、未来の水を守り育てるSTYLE。美しい道志の森の風景とともに、コップ一杯の水道水に込められた想いを、ぜひ感じてください。
横浜スタジアム約1,097個分の森を管理!?
横浜の水道水の歴史は、今から100年以上前に始まります。1916年、横浜市は市民に安心で安定した飲み水を届けるため、道志村の山林を公有林として取得しました。その広さは横浜スタジアム約1,097個分にも及ぶ広大なものです。これには、健全な森林が持つ大切な役割が深く関わっています。
雨や雪が降ると、水は森林の土にゆっくりとしみ込みながら自然に浄化され、地下水となって川へと流れ出します。さらに、森林の土はスポンジのように水を蓄えるため、川の水量を安定させ、洪水を和らげたり、水不足を防いだりする働きもあります。このように水を育み、守るために手入れされる森は「水源林」と呼ばれます。横浜市が道志村で取得した山林も、まさにこの水源林です。
ただし、この水源林が適切に管理されず荒れてしまうと、水を蓄える力が弱まって洪水や渇水といった極端な水の増減が発生しやすくなります。天然林は、すでにかん養機能が備わっている林のため、必要最低限の整備にとどめて自然の推移に任せていますが、ヒノキやスギなどの人工林は適切に整備を行わないと機能を十分に発揮できません。かん養機能を高めるため、木を間伐して森に光を入れて低木の発育を促すなど日頃から人の手による整備や保全が欠かせないのです。

山梨県東南端に位置する道志村。関東屈指の清流・道志川の源流域にあり、豊かな緑と清らかな水に恵まれた自然あふれる山村。

野毛山公園内に設置されたヘンリー・スペンサー・パーマー氏の像。約140年前、ペリー来航により開港した横浜は商業、文化の発展の地としてその人口が爆発的に増加、水不足が発生しました。その課題に対して、日本で最初の*1近代水道がイギリス人技師ヘンリー・スペンサー・パーマー氏の協力のもと、横浜の地で創設されました。

道志川の水は、高低差を利用して横浜市まで運ばれています。
しかし、横浜市が管理する水源林以外では、村の人口減少や人材の高齢化によって十分な整備ができなくなるという問題が生じています。道志村の公有林(水源林)を管理している横浜市水道局水源林管理所長の山口哲司さんは、その現状について、こう語ります。

横浜市水道局水源林管理所長、山口哲司さん
山口さん:そもそも、自治体が他県に水源林を保有しているのは非常に珍しい事例です。横浜市はこの道志村全体の約36パーセントの水源林を公有林とし、水道局が計画的に維持管理・保全を行っています。
公有林以外の森林の多くは個人が所有する民有林です。水道局が民有林を直接整備することは難しいのが現状だそう。公有林だけでは水質を十分に守れないことが、大きな課題となっていると山口さんは続けます。
山口さん:横浜市が管理している公有林と個人が所有する民有林、そのどちらも横浜市にとって大切な水源地
であるとわたしたちは捉えています。
そこで民有林の整備をサポートするために水道局として出来ることはなんだろうか。そんな思いと背景から、2004年から横浜市水道局が市民に向けて、道志村での民有林の間伐や整備を行うボランティアの募集を開始します。その反響は大きく、開始当初は活動募集をするとすぐに定員に達してしまうほど。以来、年間13回ほど実施されている森林整備のボランティア活動には、毎回およそ50人が参加。のべ参加者数は、なんと2万人を超えています。

現場集合の風景。ボランティアさん、水道局職員、みんなで安全確認をしながら森を進みます
100年を超えてつづいてきた横浜市と道志村の水のつながり。現在、その水源を守るためあらたな担い手たちとともに、未来へ向けた新しい一歩を踏み出しています。
ボランティアの手で2万本以上を間伐
民有林の整備を目的として結成された市民ボランティア団体は2008年から「NPO法人 道志水源林ボランティアの会」として、その活動の幅を広げてきました。
取材に伺ったのは梅雨を感じさせない晴天の6月半ば。道志村の森林整備活動にSTYLE100取材班も同行し、その活動を体験してきました。

出発は関内駅前。早朝、参加者が続々と集合場所に集まります

大型バスで関内駅を出発。道志村までは約1時間50分ほど
午前10時前、道志村の横浜市水道局水源林管理所に到着。すぐに山へと向かい活動を開始します。

参加者の多くは会の結成当時からのメンバーというベテランばかり。随時、ホームページなどでメンバーを募集していますが、まずは気軽に体験からはじめることも可能という、ゆとりたっぷりの受け入れ体制です。
民有林整備への呼びかけがきっかけで活動がはじまった道志水源林ボランティアの会。以来、「私たちの飲む水と水源の森は、私たち自らの手で守り育て、次の世代へと引き継ぐ」ことを基本理念に活動を続けてきました。理事長の村居さんは、これまでの活動を振り返りこう話します。

NPO法人道志水源林ボランティアの会理事長の村居次雄さん
村居さん:この約20年間に、のべ2万人の方が道志村の森林に携わり、80ヘクタールの森林が整備されました。木々にして約2万4000本の間伐です。これは多くの方が道志村という離れた土地にある水源を再認識し、自分ごとにしてきたということです。そしてこれからもこの活動を広く知ってもらうことで水資源の大切さをアピールし、市民の理解と協力をより一層広げていきたいと考えています。
一方で会の存続には課題もあると続けます。

長年のボランティアさんの後ろ姿。まるで本物の山の職人です。
村居さん:森の中で良い空気を吸って、汗をかき、お弁当を美味しく頂いて、安全に楽しく活動する、やはり、それが元気の秘訣だと実感しています。ただ、現在は会の平均年齢が70歳になっているので世代交代が必要だと思います。水源の維持は決して簡単なことではありませんが、その意義は大きくやりがいもあります。ぜひ、たくさんの方に気負わずメンバーになってほしいですね。

安全面にもしっかりと配慮されている現場。道志の森インストラクタースキルアップ研修を受講した森林インストラクターが同行し、活動をサポートします。
参加して気づく、水源のこと、森のこと。
何メートルにも育った木を、ノコギリとロープを使って一本ずつ間伐する。
道志村のボランティアが作業する現場では、木が倒れる瞬間、「どーーーん」という地響きとともに、森全体が震えるような感覚が体に伝わってきます。
そんな非日常の体験に魅せられ、横浜市民のみならず、各地から多くの方がこの活動に参加しています。間伐や森の整備といった、ふだんの暮らしではなかなか体験できない作業を通じて、参加者たちはそれぞれの気づきを語ってくれました。

都筑区から初参加の河原さん。
河原さん:参加のきっかけは水道局の募集を目にしたことでした。正直、それまでは横浜の水源が道志村にあることすら知りませんでした。でも、実際に現場に来て話を聞いて、見て、体験してみると、森を維持することの大変さを実感します。

参加者最高齢89歳の平川元美さん。発足当時から年間10回は参加しているというコアボランティア。
平川さん:木を手引きで切るって集中力が必要なんですよ。そこが面白いし、魅力ですね。

今回、JICAを通じて2回目の参加。ボリビア出身の留学生ルーシーさん。
ルーシーさん:年齢や性別関係なくいろいろな人が一緒に活動をする、コミュニティづくりとして本当に素晴らしい取り組みだと思います。なによりも日本ではこうしてボランティアにたくさんの方が参加していることに感動しました。日本から世界に広がっていってほしい活動だと思います。

間伐が進み、気持ちの良い風が吹き抜ける森
間伐によって光が入った森は、やがて新しい生命を宿した心地のよい森へと育っていきます。森の整備は水源を守るための大切なアクションですが、同時に、整えられた森は人の心を癒し、その価値や必要性をそっと伝えてくれる存在にもなっているのです。
参加した人の数だけ、道志村を想う気持ちが育ち、それぞれの行動へとつながっている、そんなことを強く感じました。
100年先につながる森づくりを
開始から約5時間で作業は終了。ノコギリで木を切る人、掛け声とともにロープをひっぱり木を倒す人、山を駆けめぐりながら安全を確認する人。共同作業によって生まれる一体感の中で、森を慈しむ気持ちを分かち合い、未来へつなぐ熱意が感じられました。
そんな“森と人との関係”をどう育てていくのか。水源地のこれからについて、横浜市水道局水源林管理所の山口さんはこんな思いを教えてくれました。

本日の作業をすべて無事に終え、みなさんは関内駅への帰路へ。お疲れ様でした!
山口さん:私たちが管理・保全している公有林では、有識者の視察や検証をもとに、10年ごとに管理プランの見直しを行ってきました。現在はその第11期目に入っています。
100年先を見据えながら、地道に森を整備していくことは、水源を守ることであり、未来の飲み水を守ることにもつながっているんです。
ボランティアの皆さん、そしてこれから携わってくださる方々が、“自分たちは良い森づくりの一員なんだ”と感じてもらえる。そんな後押しができたらうれしいですね。

道志の山から横浜へ。水はめぐる

横浜市の水源を、これから100年先へつないでいくために。
間伐された森に光が差しこみ、木々がいきいきと育つように
そこに関わるひとりひとりの行動が、未来の水を育んでいきます。
森に一歩踏み入れてみれば、水と森の深いつながりが、きっと体で感じられるはずです。
次の100年の水を守る仲間に、あなたも加わってみませんか?
*1 近代水道創設 英国人技師ヘンリー・スペンサー・パーマー氏を顧問に迎え、明治18(1885)年に相模川と道志川の合流地点の三井(現在の相模原市緑区三井)を水源に水道の建設に着手し、明治20(1887)年10月に日本初の近代水道として給水を開始。
【情報】
『NPO法人道志水源林ボランティアの会』
https://doshi-suigenrin.jp/wordpress/
(ボランティアは高校生以上から参加可能です。詳細はホームページからご確認ください。