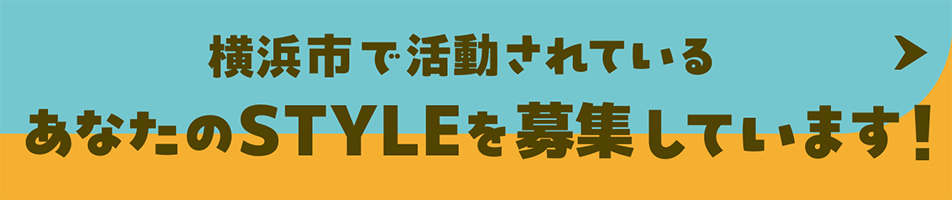サステナブルなだけじゃなく、愛される商品を生み出そう
再使用エネルギー 循環型経済
リサイクル率の低い紙製パッケージや、横浜市が保有する水源林の間伐材を断熱性に優れた「紙糸」へとアップサイクル。その糸を織った紙布から、暑さ対策のためのプロダクトをつくるヨコハマ未来創造会議のプロジェクト。
この度、その生み出されたプロダクトが発表されました。そこに込められたストーリーと想いを伺いました。
「紙糸」を活用した暑熱対策プロジェクト
日本の古紙回収率は、81.7%ともいわれています。*1(2024年時点)これは世界的に見ても高い水準と言えますが、一方で紙製容器の回収率は低く、多くは焼却されています。その背景には、禁忌品(紙資源量にならないもの)とされる紙の分別の複雑さがあります。匂いや食品残渣のついた紙は禁忌品とされ、混ざると生産工程での機械トラブルや不良品の原因になるため紙容器の分別には多くのルールがあり、それが回収率の低下にも繋がっています。
一方、森林の整備として間伐された木々も、搬出コストや形状に問題があって未利用のまま放置されるケースが多々あります。こうした資源を「紙糸」にアップサイクルし、サステナブルな商品として新たな価値を与える挑戦が始まっています。
「ヨコハマ未来創造会議」は、GREEN×EXPO 2027をきっかけに生まれた若者の共創プラットフォーム。市内の学生や企業の若手社員が集まり、環境にやさしい暮らしや社会の実現に向けて、一歩を踏み出すための場です。
そして、2025年5月から神奈川大学・道用ゼミの学生とユニフォーム製造などを手掛ける株式会社ダイイチが紙糸を活用した暑熱対策のプロダクトづくりに取り組んでいます。
プロジェクトで用いられる紙布は、お菓子などの紙製パッケージや横浜市の水源林でもある山梨県道志村で産出された未利用の間伐材をアップサイクルして製造されます。これらの資源からパルプを抽出して抄紙(しょうし)し、紙を細く裁断して撚りをかけることで糸にします。その紙糸を織り上げると紙布になるのです。
地域から出た未利用の資源を、再び地域の環境改善のためのプロダクトとして活かす「地産地環」を目指し、学生たちの自由な発想とダイイチの技術によって、紙布の商品開発は進められたといいます。

紙糸から生まれる紙布は軽量で断熱性が高いことが特徴です。また、紫外線カット効果や吸放湿性にも優れ、ムレにくく快適であることから暑熱対策素材として有効とされています。

20名の学生が5チームに分かれ、それぞれのアイデアを出し合っていったそう。

学生によるプロトタイプの中間発表の様子。レーザーカッターでレース風にカットしたポンチョは素材の特性を生かしつつ、可愛さを意識してデザインされた暑熱製品です。
そうして作られたいくつかのプロトタイプをもとに、ダイイチが学生と相談しながらブラッシュアップを重ね、扇子、フード付きTシャツ&サコッシュ、そして、晴雨兼用傘の3つのプロダクトが完成しました。
2025年9月、横浜市瀬谷区民文化センター「あじさいプラザ」で開催されたプロダクト発表会では、その実物が展示され、実用化に向けた今後の展望について語られました。

「地産地環・暑熱対策×アップサイクルプロダクト」発表会場にて展示されていた紙糸の原料。紙製パッケージや道志村の間伐について詳しい説明もあり、どんな背景から作られているか知ることができます。

GREEN×EXPO 2027の会場スタッフのユニフォームを想定して作られたフード付きTシャツ&サコッシュ。横浜の市の花である「バラ」をイメージしたコサージュも紙糸で制作。コサージュは、Tシャツ、サコッシュそれぞれ、飾る場所や花の色を自由に選択できる仕様で着用する楽しさや自由度にも配慮しています。

「涼」を感じるアイテムとして馴染みのある扇子を紙糸で製作。
「環境にいいから」だけではなく気持ちいい、楽しいから使うプロダクトへ
学生と共に本プロジェクトに尽力したダイイチの柳下元紀さんにお話しを伺いました。

株式会社ダイイチ、マーケティング部次長の柳下元紀さん。ダイイチは1953年の創業より、企業のユニフォームの企画・製造・販売を行なっています。
柳下さん:当社は企業向けのユニフォームの製造販売を通じて、社会課題、企業課題に対して向き合ってきたという背景があります。
その中で、GREEN×EXPO 2027に向けて、外部とも連携して、より新しいことにチャレンジしたいと考えていました。昨年よりヨコハマ未来創造会議のメンバーとコラボレーションさせていただいたことで、神奈川大学道用ゼミとご縁を頂き、学生と共創したプロダクト作りへの挑戦が始まりました。
これまで、ユニフォーム一筋を手がけてきたダイイチにとって新しいプロダクトを生み出すにあたり、学生との共創は新鮮だったと柳下さんは続けます。
柳下さん:GREEN×EXPO 2027に向けて、当社の技術を活かした紙布によるプロダクトの開発を考えていましたが、社内ではなかなか良いアイデアを生み出せずにいました。学生と連携することで新しい風が吹き、アイデアの壁を突破することができたと思います。今回、晴雨兼用傘をプロダクト化しましたが、我々には傘をつくるという発想自体がなかったので驚きでした。

学生のプロトタイプを元にダイイチが製品化した紙布製の晴雨兼用傘。撥水加工も施し、雨にも対応。
傘には、横浜らしさを意識したデザインを採用。レーザーカッターで切り出した紙布製のモチーフを生地部分にアクセントとしてあしらうことで、使い手により愛着を持ってもらいやすい製品に仕上げてあります。
また、別のバリエーションとして、桜の木の枝から抽出した染料で染めた桜色の傘も発表されました。桜はGREEN×EXPO 2027の開催地である上瀬谷で、倒木の危険性が高く、やむを得ず撤去されたものです。地域に愛された桜の記憶を、新たな形で継承していきたいという思いがこめられているそうです。
柳下さん:学生チームの「日常に彩りを与える傘にしたい」という姿勢やレーザーカッターで装飾をするというアイデアを取り入れ、魅力的なプロダクトになったと思います。
道用ゼミの皆さんにもプロダクトへのこだわりを伺いました。

神奈川大学道用ゼミの大久保樹さん(3年)
大久保さん:紙糸を日用品にアップデートすれば、誰もが日々の生活に取り入れやすいと思ったんです。また「地球にやさしい製品」はユーザーにとっても心地良いものなので、これを通じて紙糸を使用したプロダクトがさらに広まっていけばと感じています。

同ゼミの德永彩七さん(3年)
德永さん:紙糸からできた製品は、その役目を終えたあと土に還すこともできます。紙糸のプロダクトを知り、実際に手にとってもらうことで、資源を安易に捨てるのではなく「次の使い道を考える」ことのきっかけになれば嬉しいです。
発表会の後半には、紙糸による晴雨兼用傘の今後について「雨の日をハッピーに、使い捨て傘をゼロに」をミッションに日本初の傘のシェアサービスを展開している「アイカサ」との連携も発表されました。
GREEN×EXPO 2027の会場玄関口である相鉄本線瀬谷駅のアイカサ機器に、今回製作した晴雨兼用傘の設置を予定。市民の皆様にも使っていただけるよう調整が進められています。

日本初、スマートフォンのアプリから簡単に傘をシェアできるアイカサ。「雨の日を快適にハッピーに、使い捨て傘をゼロに」をミッションにサービスを展開。現在アプリの登録者数は75万人に上り、その利便性や環境に配慮した取組が注目されています。

アイカサを開発・運営する株式会社Nature Innovation GroupのCOO勝連滉一さん。神奈川大学出身、道用ゼミに参加した経歴も。在学中にアイカサの創業に携わる。
アイカサではこれまでも、ジップロックやペットボトルをアップサイクルした素材で、オリジナルのシェアリング傘を展開してきました。
今回、紙布の傘を取り入れるのは初めての試み。「私たちのサービスとともに紙布の傘が地域の中で循環し、傘の使い捨てゼロの未来をつくっていきたい」と語りました。
「愛着」が生まれる物を循環させよう
アップサイクル紙糸や紙布を使った製品は、まだ広く普及しているとはいえません。
これから普及させるためのヒントは、私たちが毎日行う小さな選択の中にあるのかもしれません。

同ゼミの粟野友結さん(3年)
粟野さん:今回、暑熱対策という課題を解決するための機能をどうプロダクトに盛り込むかも大切ですが、私たちは同時に「愛着が湧くもの」であることも重視しました。
サステナブルであることに加えて、デザインも可愛いものなら、より愛着も湧くと思うんです。実際にプロダクト製作を手がけてみて感じたのは、日用品はなるべく長く愛着を持って使い続けられるものを選び、むやみに捨てない暮らしの大切さでした。

未利用の資源から愛着のある物作りで使い捨てゼロの未来へ。
今回、発表されたプロダクトはまだ試作段階のもの。GREEN×EXPO 2027での実用化を目指し、今後も耐久性や防水性などの実証実験を重ねていくそうです。
*1 公益社団法人 古紙再生促進センターホームページより http://www.prpc.or.jp/
【情報】
ヨコハマ未来創造会議 https://next-gen.city.yokohama.lg.jp/
株式会社ダイイチ https://www.un-daiichi.co.jp/
神奈川大学・道用ゼミ https://doyolab.net/
アイカサ https://www.i-kasa.com/
取材させていただいたのは...
STYLE実践のヒント
「大切なのは紙製パッケージを廃棄するときに、各自治体のルールを守ってきちんと古紙として分別し、資源として回収に回すことです。アップサイクル紙糸の取り組みを知ってもらうことが、日々の暮らしの中での分別という、些細だけれど大切な行動につながる。そんなきっかけになれば嬉しいですね。」(ダイイチ・柳下元紀さん)
STYLE100編集部