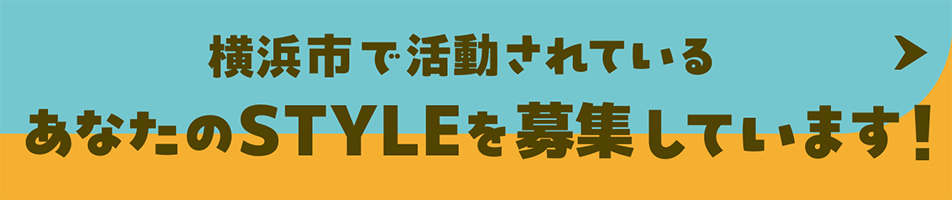花から地域に循環を生み出そう!
循環型経済 生物多様性
この記事の目次
2027年GREEN×EXPO 2027開催の地、旧上瀬谷通信施設の跡地が立地する瀬谷区。この地域を花で盛り上げる「フラワーロードプロジェクト」が始まっています。
EXPO会場のゲートウェイとなる海軍道路に花を植栽するこのプロジェクト。取材で訪れた2024年12月8日の開催日では、神奈川県立横浜瀬谷高等学校(以下、横浜瀬谷高校)の生徒の皆さんを中心に地元の小学生や様々な企業、地域の皆さんまで200名もの人々が参加し、汗をかきながらも、満開の笑顔を見せながら沿道を花で彩っていく光景が広がっていました。今回で7回目の開催という本プロジェクトですが、特筆すべきは、高校生の思いから始まったということ。どのように始まり、どのような未来を目指しているのか。さまざまな想いと未来に向けて描くビジョンを伺ってきました。

– プロジェクトに参加している横浜瀬谷高校の生徒の皆さん
閉校となる神奈川県立瀬谷西高等学校。不安な状況でこそ地域にできることを模索した、生徒と先生の想いとは。
2021年にスタートしたというフラワーロードプロジェクト。
その始まりは神奈川県立瀬谷西高等学校(以下、瀬谷西高校)
と神奈川県立瀬谷高等学校との統合で、これまでの瀬谷西高校は閉校するという局面だったといいます。

– 瀬谷西高校最終学年の生徒とともに、本プロジェクトを立ち上げ、現在も横浜瀬谷高校総括教諭としてプロジェクトに伴走する黒崎洋介先生
黒崎先生: 2021年当時、新入生も入ってこない瀬谷西高校最終学年は、学校がだんだんと縮小し、寂しさを感じていました。教員たちもなんとか生徒たちを元気付けたいと色々と模索する中で、瀬谷で開催されるGREEN×EXPO 2027は最高の地域資源になると思ったんですね。
それまで学年行事として小さく行っていた*1 ハマロード・サポーターという活動と、花で瀬谷地域を活性化させ、さらに瀬谷西高校最終学年のミッションとして地域に恩がえしをしようという想いからフラワーロードプロジェクトがはじまりました。
自分たちが卒業してしまえばもう学校はなくなってしまうという寂しさと、最終学年として出来ることをやりたい、そのような想いで始まったフラワーロードプロジェクトは地域の皆さんの協力も得ながら、閉校を迎えるその時まで、瀬谷の街道を彩るために活動を続けていったと言います。
プロジェクト始動から2年を経た2023年。瀬谷西高校は閉校、新たに横浜瀬谷高校に再編・統合されました。当初、新しくなった学校に花の植栽の風土はなかったそう。経験のない生徒たちにプロジェクトを継承していくことは決して簡単なものではなかったと黒崎先生は当時を振り返ります。
黒崎先生: 瀬谷西高校は最終学年の卒業で閉校したので、横浜瀬谷高校にこれまでプロジェクトに関わってきた生徒は当然いないんですね。プロジェクト自体、存続の危機ではありました。でも、瀬谷西高校の卒業生や横浜瀬谷高校の生徒会が中心となり、また、瀬谷西高校時代から花の植栽に参加してくれていた地域の方のご協力もあり、本当にごく少人数ですがプロジェクトは引き継がれたんです。
「奇跡的に繋がっていった」と笑う黒崎先生。
2027年まで続いていく本プロジェクト。まだまだチャレンジは続いていきますが、プロジェクト存続の危機を乗り越えて、今どんな風景が見えているのでしょうか?

– 花の苗や植栽当日に必要な水や肥料提供は、地元のJA横浜やサカタのタネグリーンサービス、瀬谷土木事務所、横浜環境保全株式会社といった企業や団体が協力。現在、プロジェクトの関係企業数は10件を超えています。
黒崎先生: いま、私たちが花を植えている海軍道路は、昔、軍用に使用されていた道路で戦争の名残なんです。そういった過去の歴史を背負った道を花で満ち溢れたフラワーロードにアップデートすることでGREEN×EXPO 2027を盛り上げる。そのミッションを生徒と共有しながら、GREEN×EXPO 2027のゲートウェイでもある海軍道路をしっかりと花で彩っていくことが2027年までの目標です。
今回で7回目の開催ですが、やはり年々関わってくださる地域団体・企業の多さに驚いています。
なぜ、これだけの団体や人々が関わってくれるのか。実感としては、シンプルですが、高校生の純粋な想いがまわりを巻き込んでいくんだなと強く感じています。
生徒たちだからこそ、立場を超えて色々な企業さんとのハブになれるんですよね。
実際、生徒が企業に出向いて連携のお願いをしていく、そこからつながって、関わりに幅がどんどんでてきて、進んでいる。それが今のプロジェクトの姿です。

花からはじまる瀬谷の新しい循環!フラワーロードプロジェクト
閉校という局面と向き合い、地域への恩返しとGREEN×EXPO 2027を盛り上げたいという生徒の想いから始まったフラワーロードプロジェクト。横浜瀬谷高校に受け継がれて2年目の今、さらなる一歩は着実に動き始めていました。
黒崎先生: 今は“花の循環”を意識した「フラワーループ」の活動を一歩づつですが、生徒たちと実現しているところです。これまでも、フラワーロードプロジェクトで使用する花苗は、地産地消にこだわり、フラワー持田園さんなど、横浜市内産の花を使用していました。現在では、こうした地域経済の循環だけでなく、花を起点とする様々な循環に取り組んでいます。例えば、フラワーロードに植えた花は瀬谷で養蜂に取り組む一般社団法人セヤミツラボさんのハチミツの蜜源にもなっています。また、同じ瀬谷でリサイクル事業などを手がける株式会社ライプロンコーポレーションさんと、花苗を植えているプラスティック性のポットをゴミ袋に再加工してもらうという試みも始まっています。そして、サカタのタネグリーンサービス株式会社さんと連携して、イベント等で使用した後のロスフラワーを活用することにも取り組んでいます。こうした花によるサーキュラーエコノミーの実現こそが、“花の循環”を意味するフラワーループです。

– 余った花苗を小学校や特別支援学校にお裾分けすることもあるとか。その際も先々でポットを洗ってもらい、横浜瀬谷高校の生徒さんが回収、リサイクルへ。回収にいくことで生まれるコミュニケーションもフラワーループです
黒崎先生: 花の命は一年で終わりですがそこからまた受け継がれていくものがあって。
枯れた花も将来的には堆肥にする構想があったり、フラワーロードプロジェクトから生まれるフラワーループを、GREEN×EXPO 2027を控える横浜・瀬谷で生み出していくことが、今後の目標でもあります。
プロジェクトからどんな循環を生み出すことができるのか。同校の教育プログラムから派生した有志団体である「未来共創ラボ」代表の吉森遥輝さん(1年生)はそのやりがいをこう話します。

– 先輩からの襷を受けフラワーロードプロジェクトに参加する吉森さん。横浜瀬谷高校「未来共創ラボ」の生徒さんは自分のプロジェクトに基づいて肩書きを記した名刺を持っているそう。その名刺を持ち企業へ地域の商品開発の交渉に足を運ぶのはもはや日常だとか。
吉森さん: GREEN×EXPO 2027開催時には、ここ瀬谷にいろんな国の方が足を運んでくださいます。より深く瀬谷の魅力を伝えられるようなことができたらいいなと考えています。なにより、自分たちで何ができるのか、それを模索しながら実際手足を動かして生徒主体で向かっていけることにわくわくしています。
瀬谷の一般社団法人セヤミツラボとコラボ、フラワーロードの花も蜜源にした百花蜜をつくったり、瀬谷の魅力のつまったお土産とはなにか思考をめぐらせたり。横浜瀬谷高校主導のもと、すでに実現している企画も伝えてくれた吉森さん。生徒ひとりひとりのフラワーループは、ものをつくる、サービスを生む、だけではなく、ひとりひとりの成長にも深くつながっていく、そんな嬉しい期待を感じました。
GREEN×EXPO 2027で世界中の人を瀬谷の花でもてなしたい!身近な花から、地域に新しい循環を生す未来
生徒が地域にダイブして様々なつながりをつくりながら、関係人口の幅、仲間を増やしていく、フラワーロードプロジェクトは地域循環型プロジェクトとして今まさに地域を豊かに耕しています。
改めて、GREEN×EXPO 2027の開催を見据え、そしてその先の未来に見ているのはどんなビジョンなのか。横浜瀬谷高校・小林校長先生に伺いました。

– 瀬谷西高校でも校長としてプロジェクトを支えてきた小林幸宏校長先生。
小林校長: 学校の一番の育成目標に、持続可能な社会の創り手として、これからの社会で活躍できる力を育てていくというものがあります。GREEN×EXPO 2027が終わった先にもこの地区には様々な開発が行われていくかと想像しています。
その場面において、持続可能な街を私たちがつくるんだという意識を持った生徒たちを育む、そんな学び舎でありたいと思っています。
持続可能な社会の創り手として、これからの社会で活躍できる力を育む学び舎としてできることとは。小林校長はこう続けます。
小林校長: これからの社会で活躍する力とはどんな力なのかを念頭に、*2 グラデュエーション・ポリシーというものを掲げています。ひとつは課題を解決する力、そして0から1をつくる力、そのためには、間違えると恥ずかしいから発言しない、のではなく、失敗をしてもよい学校の雰囲気づくりを心掛けています。
卒業までにこのような力をつけ、心のエンジンが駆動できる、自分で自走できる生徒を育てることが最終目標なんです。

– 横浜FCクラブマスコットのフリ丸と花を手に記念撮影も
生徒が名刺を持ち、自分たちで企業に赴き熱意を伝えて巻き込んでいく。
フラワーロードプロジェクトからさらにおもしろい循環が生まれる、そんな生徒のパワーに「びっくりします」と小林校長は笑います。
小林校長: こちらが用意せずとも生徒たちは地域にダイブして企業とつながっているので。正直、生徒たちの力にびっくりすることは多いんです(笑)
すごいなと。
学校で教わっていることだけ、学校の中に閉じこもっているだけではない学び、実践がこれからは大事かなと思っています。どんどん社会に開かれた教育課程がここでは実現できていると自負しています。
GREEN×EXPO 2027開催まで、そしてその先の未来まで。横浜瀬谷高校と地域がどんな風に醸され、フラワーロードプロジェクトの花とともに世界中に広がっていくのか。あなたもその創り手になってみませんか?
プロジェクトはいつでも開かれていますよ。
—————————-
*1 ハマロード・サポーター 地域の身近な道路を対象に、地域のボランティア団体
と行政が協働して、身近な道路の美化や清掃等を行っていこうという制度
*2 グラデュエーション・ポリシー 学校教育活動を通じてどのような資質・能力を育むことを目指すのかの指針