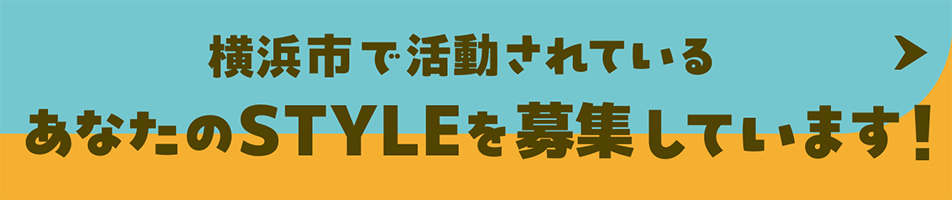横浜の物語と食を一緒にたのしもう!
循環型経済
この記事の目次
横浜市では、地域課題解決につながる取り組みのなかで生まれた食を「ストーリーフード」と名付け、新しい食の楽しみ方として注目しています。そんなストーリーフードについて、もっと深く知ることができる機会が『ヨコラボ2024』で設けられました。『ヨコラボ2024』とは、複雑化・多様化する社会課題の解決に向けた、行政や多様な主体による協働・共創の取組をさらに推進していくための公民連携の発信・対話の場として開催されたイベント。今回は、本イベントに、横浜市を拠点に活動する団体やプロジェクトが終結。プロジェクトの背景にあるストーリーや想いについて、その一部をご紹介します。

物語のある食「ストーリーフード」を拡げよう!
11月2日(土)横浜市庁舎の一階アトリウムで開催された『目指せGREEN×EXPO 2027 ! 〜ストーリーフード・よこはま未来の実践会議〜』。会場には、10の「食」に関する団体や生産者が集まりました。活動拠点は、鶴見区・西区・中区・金沢区・緑区・青葉区・港北区・泉区・瀬谷区とさまざま。そして会場に並んだのは、野菜や小麦粉、ハチミツ、オリーブなど色とりどりの食材たち。これらのほぼすべての商品が横浜市内で生産されていることに驚くと同時に、それだけ多くの想いを持った方たちが商品の開発を通じて様々な課題解決に挑もうとしていることをしていることにワクワクします。各ブースでは商品を販売するだけでなく、その商品によって解決したい課題や、叶えたい未来、実際の生産現場のお話しなども積極的に発信。イベントを訪れたお客さんたちも、熱心に耳を傾けながらお買い物を楽しんでいる様子でした。
毎日を豊かにしてくれる”語れる食材”たち。
オリーブが、横浜の「食」も「農」も元気にしてくれる(横浜オリーブ)
「横浜市にオリーブ農園がある」という話を聞いて、驚く方も多いのではないでしょうか。横浜オリーブは、横浜市緑区鴨居を拠点にオリーブを栽培し、商品化に取り組むプロジェクト。現在も栽培中であるため、ヨコラボでオリーブの実の販売はしていませんでしたが、ブースにはお料理に使えるオリーブの葉のパウダーや、オリーブの木を使った犬用おもちゃなどが並びました。横浜オリーブのプロジェクトの背景にあるストーリーをプロジェクトメンバーのみなさんに聞きました。

耕作放棄地を再生する手法としてオリーブを育てるプロジェクトが生まれたこと、さまざまな方々が連携しながら少しずつ作付面積を増やしている現状を伺いました。
「私たちが解決したいのは、横浜市に限らず国内全体で問題視されている耕作放棄地の問題でした。耕作放棄地をそのままにしておくと、害獣の被害や水害などの原因にもなってしまいます。横浜オリーブは、耕作放棄地をオリーブ農園として復活させ、横浜で高級オリーブを生産することを目標に掲げて活動しています。横浜には飲食店が多く、また近隣には東京という一大消費圏があります。横浜でオリーブを栽培し、商品化することができたら地産地消の推進にもつながります。横浜オリーブが、農業の課題も食の課題もどちらも解決することを目指しています。」
食用のオリーブの栽培はもちろん、オリーブの葉や木も活用したアイデア商品で、廃棄のない商品開発に取り組んでいる横浜オリーブ。横浜市の耕作放棄地が生まれ変わり、地球にやさしいオリーブの産地として日本中に名を馳せる日も遠くないかもしれません。

オリーブオイルなどのプロダクトも販売。まだ収量が少ないため、他の地域のプロダクトを販売するなどしながら、オリーブの魅力を伝えているとのこと。
「もったいない」を「美味しい」に変える、金沢区の青みかん(アマンダリーナ合同会社)
青みかんとは、温州みかんの若い果実のことを指します。栽培の過程で、青い状態のみかんを間引くことで、残りの実に栄養を行き渡らせ美味しい温州みかんを育てます。アマンダリーナ合同会社の代表奥井奈都美さんは、この間引いた青みかんを廃棄することなく美味しく活用する方法を考えるプロジェクトを立ち上げました。ブースには、青みかんジュース、ドレッシングにポン酢など奥井さんのレシピから開発された商品が並びます。もったいないを美味しいに変えるプロジェクトが、大きく育ったストーリーについてもお話しいただきました。

農園での収穫の様子、商品が生まれるまでのさまざまな連携パートナーさんたちとのストーリーを丁寧にご紹介してくださるアマンダリーナ代表の奥井さん。
「廃棄する予定の青みかんを活用して、ジュースやドレッシングを開発したり、またそれらを活用したレシピを発信していた私たちですが、そこから地元の企業や学生のみなさんとコラボレーションをして、さらに広く商品を展開する機会にめぐり会うことができました。たとえば、青みかんの皮を使った『金澤八味』。こちらは、開発には地域の小学校、製造には養護学校の生徒さんが参加してくださっており、地域連携から生まれた調味料になりました。また、地元企業の方からの提案で、青みかんの搾りかすや精油を活用した『よこはまの森洗剤』という商品も生まれました。こちらは、使用後の排水が海の水を綺麗にしてくれるという商品。エコにもこだわり、量り売りでの販売に取り組んでおり、市内外のエコステーションでの販売を行っています。」
横浜市金沢区の青みかんをハブにして、さまざまな団体が連携し地産地消の枠を超えて、地球にやさしい商品開発を行うことができているようです。「もったいない」を「美味しい」に変え、そして未来の暮らしも支えてくれる、ストーリーが広がり続けるようなプロジェクトでした。

ドレッシング類は特に人気があり、売り切れてしまう場所もあるそう。廃棄せず、摘果みかんが美味しいプロダクトに生まれ変わる取り組み、素晴らしいですね。
“循環型”ゴミ処理による『ハマのありが堆肥』(横浜環境保全株式会社)
横浜環境保全株式会社のブースで行われていたのは、野菜の詰め放題。人の顔の大きさほどある立派なさつまいもや、菊芋、里芋、にんじんなど、さまざまな野菜が並んでいます。実は、こちらのブースで発信しているのは、この野菜たちではなく、それらが育つ際に使われた堆肥『ハマのありが堆肥』。横浜環境保全株式会社は、横浜市の一般廃棄物や産業廃棄物、資源ごみの運搬・分別・処理を行う事業会社です。ゴミの処理と、堆肥にどのような関係があるのか、そのストーリーを広報・PR推進役の荒川義則さんに伺いました。
「普段からゴミ処理事業を行っている私たちは、日々大量のゴミを目の当たりにしてきました。飲食店なども多い横浜市では、生ゴミや食品残渣なども多く、焼却処分する際の二酸化炭素の排出量も今後問題視されると考えています。焼却処分ではない方法で、大量の生ゴミを処理し、かつ暮らしに役立てるような形で利活用できないか。そう考えたときに挑戦したのが堆肥化処理でした。生ごみを粉砕し、発酵させ、有機物質の豊富な堆肥へと変換する。横浜環境保全株式会社というゴミの運搬・処理を行っている私たちだからこそ、余計なコストや二酸化炭素の排出は抑えながら、ゴミを堆肥化処理することができました。そうして完成したのが、『ハマのありが堆肥』です。現在はこの堆肥を使って県外の畑で野菜を育てています。そして、契約している横浜市の飲食店に野菜を卸すことで、生ごみの循環型処理を叶えています。」
実際にこの堆肥を使っている農家さんからは「野菜の成長が早い!」「色もよく、とても美味しい!」との声が寄せられているそう。有機100パーセント・無添加の堆肥だから、安全面からも高い評価を受けているようです。ゴミ処理を担う企業が挑戦するからこそ実現できた、ストーリーに溢れた野菜たちが、これからの横浜の飲食店や食卓を彩ってくれそうです。

食品残渣が豊かな堆肥に。そこからまた美味しい野菜が育つ。素晴らしいループが生まれています。堆肥に変えるための工程もあり、まだまだたくさんの堆肥を生み出すまでにはさらなる工夫が必要とのこと。
作り手も、消費者も。物語で日々の暮らしをもっと豊かに。
食を入り口にして、横浜市の土地や気候の特徴を知ったり、熱い想いのある人や企業の存在に気づくことができたストーリーフード。それだけでなく、普段はなかなか考える機会のなかった社会課題や環境問題について知るきっかけにもなりました。そして、それぞれのストーリーフードの作り手のみなさんも、今回のようなイベントで直接、消費者の方とコミュニケーションを取ることで、率直なリアクションや意見をもらったり、新しい角度からのアイデアをもらったりと、刺激を受けるシーンも多くあったようです。これからそれぞれのプロジェクトがどのように展開していくのか、また新たにどのようなストーリーフードが生まれるのか楽しみですね。
食べるだけでなく、背景にある物語も一緒に味わう、新しい食の楽しみ方「ストーリーフード」。作り手の物語を知り、商品を購入し、味わうことが応援につながります。そしていつのまにか、そのアクションが私たちの暮らしを豊かにすることにもつながっているのです。「ストーリーフード」という食の楽しみ方、あなたもはじめてみませんか。
出店者
横浜オリーブ
一般社団法人 セヤミツラボ
横浜環境保全株式会社
社会福祉法人 開く会
横浜あおば小麦プロジェクト
株式会社木曽屋
NPO法人 KUSC
アマンダリーナ合同会社
幸海(さちうみ)ヒーローズ
NPO法人 アニミ
株式会社よこはまグリーンピース
NPO法人 街カフェ大倉山ミエル