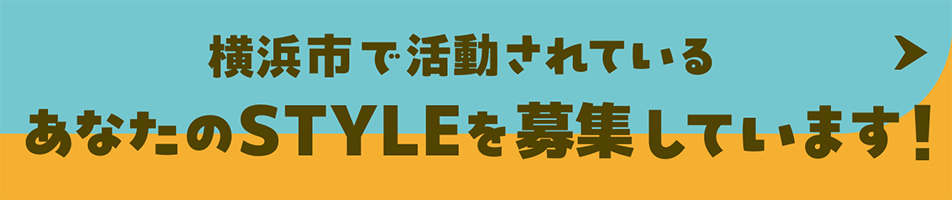若者のアイデアで、横浜を彩ろう!
生物多様性
この記事の目次
横浜市で2023年から開催されている、『ヨコラボ(YOKOHAMA Co-lab.)』。今年は、複雑化・多様化する社会課題の解決に向けた、行政や多様な主体による協働・共創の取組をさらに推進していくための公民連携の発信・対話の場として『ヨコラボ2024』が開催されました。そのプログラムの一つが、11月2日(土)横浜市庁舎の一階アトリウムで開催された『目指せGREEN×EXPO 2027! 〜ストーリーフード・よこはま未来の実践会議〜』です。
今回は、こども・若者がGREEN×EXPO 2027に向けて自分たちには何ができるかを学校や地域を超えて議論し、提案までつなげる「よこはま未来の実践会議」で実施された『若者実践チーム』による参加型プログラムについてご紹介。主催チームの高校生たちの意気込み、未来の横浜に寄せる思いなどを語ってもらいました。

「参加しやすい」社会を、未来の主人公たちの手でつくる。
突然ですが、横浜市に住む子どもや若者たちが、横浜市という街のことをどう思っているの
か考えたことはありますか?さまざまな制度や新しい取り組みによって、少しずつ住みやすい街になっていく横浜市ではありますが、横浜市の小学生、中学生、高校生、大学生などいわゆるこの街の未来を担う若者たちは、変わりゆく横浜で普段どんなことを考えながら過ごしているのでしょうか。
「よこはま未来の実践会議」は、そんな子どもや若者が主人公になって、横浜市の未来のこと、自分たちのこれからのことをじっくり考える場としてスタート。今回は、『ヨコラボ2024』のプログラムの一環として、子どもや若者たちが普段考えていることを、子どもや若者自らの言葉で提案してもらいました。朝から開催された本プログラムは、横浜市の小・中学生で構成する『こども実践チーム』による、各地域と連携して実施されたプロジェクトの報告から始まり、小学生たちへのインタビューや、市長との交流の場など、さまざまな方法で子どもたちの声を横浜市へ届ける取り組みが行われました。午後からは、市内の各高校の有志の実行委員や、大学生サークルの皆さんで構成する『若者実践チーム』による活動発表を実施。GREEN×EXPO 2027に向けて、いま若者たちに何ができるのか次々と意見を提示しました。
そして各校の活動発表の後に実施されたのが、『若者実践チーム』のメンバーによるワークショップです。横浜市青葉区を対象に、青少年の地域活動拠点として多くの中学生や高校生が集まる「あおばコミュニティ・テラス」のチーム等がファシリテーターとなって、この場で若者たちの声を集め、アイデアを届けるワークショップ形式の会議に挑戦しました。
ワークショップでは、各チームから大人顔負けの視点で様々な意見が挙がりました。たとえば、「公共空間に置かれている椅子には、ホームレスの人たちが横になれないようなデザインを採用するという事例を見たことがあります。そういったデザインを採用することは、本質的な課題解決にはつながりません。ホームレスの方々がどうすれば仕事に就けるのか、家を借りることができるのか、そういったアプローチができる自治体になって欲しい」という意見。
そのほか、「廃墟や空き家など治安の悪い印象を持つエリアがあることが気になります。そういった場所はゴミのポイ捨てや路上喫煙の増加にもつながってしまう傾向があると感じています。街路樹の整備などをおこなって、街の明るい場所を増やすように工夫したり、住民みんなで掃除をする日を作って、街全体へ住民たちの目を行き渡らせることも必要なのではないか」など、課題に対して表面的な解決策を提案するに止まらず、根本的なまちづくりへのアプローチや、ハッとさせられるような意見も集まりました。
短時間でありながらも、各チームがしっかりと話し合いそれぞれの意見を組み立て、提案することができたワークショップ。今回の成功の背景にあったのは、ワークショップを企画・実践した若者たちによるチャレンジでした。未来の主人公である若者が自ら企画し、若者が語る、そんな新しいスタイルの取り組みだったからこそ、独創的で若者らしいアイデアが豊富に生まれたようです。ワークショップのファシリテーションをつとめた「あおばコミュニティ・テラス」のみなさんに、今回のワークショップでのチャレンジについてお話しを聞いてみました。

「よこはま未来の実践会議」の様子。このイベントで初めて出会った者同士がチームを組み、対話の中から課題を決めその解決に向けてアイデアを出し合うスタイル。
若者が企画し、若者が未来を語る「未来の実践会議」が始動!
学校でも家庭でもない「サードプレイス」であるとともに、若者の社会参画に興味のある学生たちが集まって、自主的に活動しているという「あおばコミュニティ・テラス」。普段から自分たちがもっと過ごしやすい青葉区であるためにどんなことができるのか、若者自ら、ゼロから施策を練って、提案するプログラムを実践しているのだそう。
いままでは青葉区を対象にしてアイデアを組み立てきましたが、この取り組みを、横浜市全体へ視野を広げて実践できないかと考えたメンバーたち。そして、中学生から大学生までの若者たちを巻き込んで、みんなが考えていることやアイデアを提案する場が今回の「よこはま未来の実践会議」で実現しました。
テーマは「まち肯定感を持てる横浜市」。ありのままの横浜市の姿を、これからもずっと好きだと言えるように、今どんなことができるのか。それを考えるために、まずは、自分たちと同世代である若者たちに、身の回りの暮らしや街の様子から課題に感じていることや困っていることについて聞き出し、その解決策となるアイデアを提案してもらいました。
「まち肯定感」を持てる横浜になるにはどうすればいいのか、若者たちはどんな課題を感じていて、どんなふうに課題を解決していくことができるのか。参加したメンバーたちは、まず個人ワークで自分自身が感じている課題や困っていることをまとめ、それから5名程度のチームを作ってワークショップ形式で話し合いを進めていきます。

一人ひとりが真剣に横浜の未来について対話する時間、この体験、経験が次の未来につながるはず。
初めて顔を合わせる中学生・高校生・大学生らが短時間で自分たちのアイデアをまとめてプレゼンするなんて、なかなかレベルが高いワークショップ。主催したメンバーは、ワークショップを企画・開催する際には、工夫したことがたくさんあると話してくれました。
「特に大切にしたのは、全員が気軽に意見を出し合えるような空気を作ること。いきなりチームで話し合うのではなく、まずは個人ワークで考えをまとめることで、その後のワークも自分の思いや言葉を大切にしてもらうように設計しました。また、チームを組んでからのワークでは、まずは各チームの共通の目標を『中核』に掲げることからスタートしてもらいました。その中核に向けて具体的にどんなアクションが必要なのか、誰にどう動いて欲しいのかを考えることでそれぞれのチームが、理想や目標からずれることなく、さまざまなアイデアを出し合うことができたように思います。」(高校生)
企画の際には、みんなで何度も集まって何時間も打ち合わせをし、ワークショップの設計や雰囲気作りについて意見を出し合ったのだそうです。

プログラムの企画を担当した 「あおばコミュニティ・テラス」のメンバーの中学生
このように意見をまとめるプロセスも工夫することで、短時間でありながら、各チームがそれぞれの視点で話し合い、独創的で若者らしいアイデアを提案することができたワークショップ。大人たちも顔負けのアイデアやプレゼン力で、横浜への想いをしっかり伝えてくれました。
目指すのは、みんなで考え、語り、創る横浜市。
ワークショップを終えて、主催チームのあおばコミュニティ・テラスのメンバーからはこんな感想が寄せられました。
「想像していた以上に、参加者のみなさんが意見を持って話し合いができていてすごいと思いました!」「今回のワークショップをきっかけに、学校や団体の枠を超えて、新しいつながりが生まれていったらいいな。」「誰もが主役になって自分の思いを語れることをとにかく大切にしていたのですが、みんなそれぞれのチームで積極的に意見を伝えている姿が見られてよかったです。」などなど。

「よこはま未来の実践会議」の発表の様子。それぞれのチームで出たアイデア、そのプロセスで感じたことを自分たちの言葉で発表していく。
今回の成功の背景には、主催者が中学生・高校生であることも挙げられるのではないかという意見もありました。
「正直、このワークショップを大人が企画・開催していたらこんなに上手くいかなかったんじゃないかなと思います。主催している僕たちも同世代だから、僕たちが悩んだり、あたふたする様子も伝わっていて。だからこそ、参加者みんなも耳を傾けやすくなって、参加する意思みたいなものが作られやすくなったのではないかな。」(高校生)
若者たちが自ら企画し、若者たちが語る。シンプルではありますが、若者たちの声を集めるのに同世代のパワーは必要不可欠なのかもしれません。
今回は『まち肯定感』をテーマにワークショップ行ったみなさん。では主催のあおばコミュニティ・テラスのみなさんは、これからもずっと横浜という街を好きだと思えるために、どんなことを望んでいるのでしょうか。
「今回、私たちは子どもや若者が考えている課題や困っていることをしっかり言語化することができました。このワークショップで完成したのは、横浜市への意見書のようなものです。これから、これらの意見やアイデアを形にしてくれたり、若者たちの理想の実現に向けて横浜市が新しいアクションを起こしてくれてこそ、『まち肯定感』は大きくなっていくと思います。聞いて終わりではなく、その先のアクションに期待したいですね!」(複数名回答)

プログラムの企画を担当した「あおばコミュニティ・テラス」のメンバーの大学生。
さらに、子どもや若者の意見に耳を傾けるという点についてもこんな意見がありました。
「若者の声を聞きたいからと言って、ただ漠然と『どんなことを考えているのか教えて!』とインタビューするだけでは、本当の思いを聞き出すことはできないと思うんです。小学生でも中学生でも、突然マイクを向けられても困ってしまいますよね。でも、今回のようにワークショップをやってみたり、手紙を書いてもらったり、ゆっくり話せる場を作ったりしたら、きっとみんな自分の思いをたくさん語ってくれると思います。『若者の声を聞いてくれる横浜』であるために、『若者たちが声を発しやすい、届けやすい横浜』であることを忘れないでほしいと思います。」(大学生)
若者たちが自ら考え、対話を続けることで見えてくる未来。出てきたアイデアや考えを、大人たちがいい悪いで判断したり、評価するのではなく、一貫して若者たちが考え、対話し総括する。この「よこはま未来の実践会議」は始まったばかり。ここで行われた1つ1つの対話が、明日の横浜をカタチヅクルことにつながるのではないでしょうか。
”目指せGREEN×EXPO 2027!”と銘打って開催した今回の「よこはま未来の実践会議」。しかし、私たちのゴールは決して2027ではありません。GREEN×EXPO 2027が終わってから、その先もずっと子どもたちや若者が横浜市を好きだと言える街であり続けることが重要です。
誰もが『まち肯定感』を持てる横浜市であるために、まずはみなさんが普段感じていることや困っていること、考えていること、声に出してみてはいかがでしょうか。
そして、今まで以上に、子どもたちや若者たちの声に耳を傾けてみませんか。