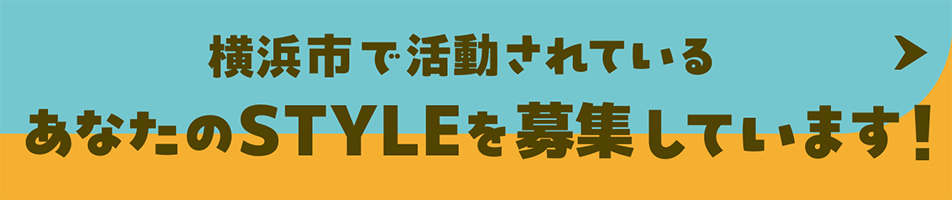クラフトビールでフードループを生み出そう
再使用エネルギー 循環型経済
この記事の目次
ビール文化発祥の地、横浜。その中でもみなとみらいエリアは、クラフトビール醸造所(以下ブルワリー)が6つも存在する日本有数の地であり、クラフトビールの街と言えます。そんな横浜で創業26年、横浜のクラフトビールの代表とも言える“横浜ビール”はブルワリー併設の「横浜ビール本店レストラン UMAYA」で出来立てのビールを味わうことができたり、最高の乾杯を提供すべく、ランニングイベントを開催していたり。「わくわく、つながる」をキーワードにした取り組みはどれもユニークかつ興味深いものばかりです。今回はそんなビールにまつわる様々な取り組みのなかから、廃棄される「モルト粕」の循環型有効活用について伺いました。
横浜ビールを作るときにでる「モルト粕」。
ほとんどが廃棄されてしまっている仕込み毎300kgものモルト粕を資源として社会に
2018年より、横浜ビールではビール作りの工程ででるモルト粕の循環型再利用を目指すプロジェクト「フードループ」に取り組んできました。横浜ビールが取り組むフードループとは?そこにはどんな想いと道のりがあったのでしょうか。
横内さん:これはどこのブルワリーも抱える課題なのですが、ビールを仕込むと原料である麦芽の抜け殻、いわゆるモルト粕ができるんですね。横浜ビールでは一回の仕込みで300kgのモルト粕がでます。通常は産業廃棄物としてお金を払って業者さんに委託し廃棄するのですが、これはコストでありなにより、原料にこだわって作っているビールの副産物なのに廃棄するのはもったいない。有効活用の道を考えるのはごく自然なことなんです。

横浜ビール・広報担当の横内勇人さん
美味しいビールを作ると同時に必然的に生まれるモルト粕。横浜ビールにおいてその有効活用のヒントは水にあったと横内さんはつづけます。
横内さん:横浜市の水源のひとつは100年以上前から山梨県の道志村です。約9年前、道志村の湧水を使ったビールを仕込むという試みがはじまり、それからは道志村とより絆を深めていきました。地元の農家さんともつながって道志村の野菜を横浜に持ち帰り、近隣の飲食店さんに販売したり、横浜ビールのレストランでも提供しています。そんな関係性のなかで野菜を育てるための堆肥に着目したときに、うちのモルト粕やレストランで出る端材を堆肥にし、その堆肥を道志村の農家に使ってもらう。そしてできた野菜はまたこちらで消費すると循環の輪が生まれますよね。そこで、横浜で有機100%の堆肥「ハマのありが堆肥」を製造している横浜環境保全株式会社さんの協力を得てモルトを堆肥にして届けるというフードループが実現しました。

仕込みの際にでるモルト粕。リサイクルや廃棄処理業務を行う横浜環境保全株式会社が仕込み毎に収集。堆肥への再生率は99%以上だそう。
モルト粕を堆肥にし、道志村で野菜を作る。できた野菜は横浜で消費するというフードループ。一見、順風満帆な取り組みですが、じつは、ブルワリーの課題だけではなく日本各地にある過疎、高齢化という課題も。
横内さん:道志村の農家さんは自家消費分の野菜、もしくは道の駅で販売するのみの人も多いんです。
高齢化も進み農業を継続できないという現状もあります。と同時に若い人が移住してきて農業をはじめるけれど販売先がないというケースもあって。モルト粕の堆肥をきっかけにもう少し横浜の方々との橋渡しができ、道志村の野菜の消費が増えていけば、道志村自体の活性化につながり、移住してきた人たちの農業にも貢献出来れば良いですよね。水源の川上と川下の関係のなかでこちらだけが活性化するのではなくて、どちらもという環境がフードループでもっと実現できればと思います。

道志村の農家さんへモルト粕堆肥を届けに行くことも。横浜ビールスタッフもいっしょになって土に蒔いていきます
横内さん:横浜ビールは道志村と関係があって、堆肥として使ってもらうことができる。使ってもらえるなら一方的ではなく循環型がいいのではという流れからフードループが生まれています。
私たちがビールを作る上でフードループを行うことは、使命感というより、モルト粕を廃棄するものから、必要とされる場所で生かされるものとして循環させるほうがいいというシンプルな想いなんです。
ビールのモルト粕がクラフトビールペーパーに!
廃棄物を社会で活用するフードループの新しいつながり
モルト粕からつながるフードループ。4年前からは横浜ビールのモルト粕を使い、世界唯一の試みも動き出しています。フードロスから地域にサーキュラーエコノミーを生み出す株式会社kitafuku*2が横浜ビールのモルト粕から作るクラフトビールペーパーのプロジェクトです。
すでに4年前から商品展開をはじめ、国内では「JOIF COLLABORATION BATTLE 2023」(ジャパンオープンイノベーションフェスの一環)最優秀賞を受賞。コンセプトやプロダクトにおいても関心を集める他、海外においても23カ国から問い合わせがあるほどクラフトビールペーパーへの注目度は高まっています。

モルト粕から生まれるクラフトビールペーパー。飲食店にとどまらず、子供向けのワークショップの塗り絵やノートなどユーザー目線の商品も。
「クラフトビールペーパーの構想はまさにここ横浜ビール本店レストラン UMAYAからはじまった」と話すのは、kitafuku代表の松坂匠記さん。

kitafuku代表松坂匠記さん。2019年IT職から一転、地域課題を二人三脚で解決する会社kitafukuを立ち上げる。
松坂さん:kitafukuという会社を立ち上げ、最初はフードロスからサーキュラーエコノミー事業をつくろうと思っていました。知人の紹介で横浜ビールさんのレストランUMAYAででるフードロスの課題を伺いに訪れたのですが、そこでビールのモルト粕の廃棄量を知り、これが本当の課題なんじゃないかというところに行き着きました。
「実はモルト粕という存在自体知見はありませんでした。」と松坂さん。
モルト粕を使った紙を作る。当時はまったく未知の領域だったと松坂さんは笑いますが、前職の仲間で現在は紙の卸し事業を営む株式会社ペーパル*1取締役の方の協力もあり、半年ほどで試作紙が完成したと言います。
松坂さん:なぜモルト粕から紙なのかとよく聞かれますが、紙は原材料を水に溶かすという工程があります。モルト粕は最初から大量の水分を含んでいるもの。アップサイクルするとなると脱水乾燥をしなくてはいけないケースが多いのですが、紙となると脱水をしなくてもいいわけです。
そしてもうひとつ、廃棄していたモルト粕をお客さんの手に届く形に変えると着想したときに紙にすると、例えばメニュー表やコースターとして目にすることもできるし、従業員の方の名刺にして、自分たちのビールづくりを語るきっかけにもなる。ちゃんと届けるところまで付加価値をつけていきたいなという想い、そういう背景もあって紙にしました。

ユーザーのアイデアで生まれた横浜デザインのファイル。
紙にする工程においてモルト粕配合率の調節や印刷会社との連携などのさまざまな課題をのりこえて唯一無二のクラフトビールペーパーが誕生したそう。
試作品から様々なプロダクトが生まれ4年目。横浜ビールにはじまり、いまでは全国で9件のブルワリーのモルト粕を紙にアップサイクルしてきました。2024年時点で回収したモルト粕は1600kg以上に。今後の回収量をあげるには、やはり紙自体やプロダクトのさらなる認知と流通が不可欠と松坂さん。これからのクラフトビールぺーパーとブルワリーとの関わり方についてこう語ります。
松坂さん:まず横浜から始めたこの取り組みを全国に広げていきたいと思って動いています。
ブルワリーのまわりに田畑が少なく、飼料としてまくことができないという条件を抱えているブルワリーさんは全国にたくさんあります。今は福岡でも動いていて、地域のブルワリーから出たモルト粕をその地域の製紙工場で紙にして、地域の印刷会社で印刷加工していく展開にしたいという構想です。商品開発においても、使ってくださる方が増えるとそれだけ使いかたのアイデアも増えるんだなと実感しています。最初はドイツのメディアの方が取材にきてくださって、そこから海外での認知も増えてきました。イタリアのデザイナーからユーロで買えないの?と問い合わせも。さまざまな地域、いろんなひとたちを巻き込みながら一緒になって商品開発も市場も広げていけたらと思います。
食からもっと、心動かすつながりを。人と地域の新しいつながりを作る未来
“人と人を繋ぐビールで横浜のくらしにワクワクを!”
横浜ビールのホームページを開くとこんなキーワードが飛び込んできます。
改めて、ビールの作り手としてビールだからこそできるつながり、ビールだからこそ描ける未来づくりについて伺いました。

横浜ビール広報担当・工藤葵さん。
工藤さん:ビールにはビールならではの立ち位置があるのかなと感じているんですね。それは、人と人をつなげる力だと思っていて。それがビールの魅力だと思っています。私たちは「人と人を繋げるビールで横浜の暮らしにワクワクを」というテーマを掲げ多くの方に届けたいという信念のもとビールを作っています。それは単に横浜ビールという名前だから地元横浜の人に飲んで欲しいというだけではなくて。横浜ビールをもっと身近に感じてもらい、さまざまな生活のシーンでつながることでより一層ビールやこの街の暮らしを楽しんでもらいたい。そういう場をたくさんつくっていくことがこの街に必要とされる私たちのあり方なんじゃないかと思うんですね。
ビールを作るだけじゃない、つながるビールを。
そこには一杯の乾杯からつなげていく仕掛けもつくっているとも。

こだわりの素材から美味しいビールが生まれ、でたモルト粕からストーリーのある紙が生まれる。
横内さん:毎月一回ランニングイベントを無料で自主開催していて5,60人のランナーが集まります。これはこちらが積極的に呼びかけているわけではなくて、参加した方が「すごくいいよ」と仲間を連れてきてくれるんです。そうやって全国からランナーが参加してくれるようになりました。
ゆっくり走ったあと、最後にビールを一杯提供して、みんなで乾杯をするんです。ランニングというキーワードが入ることでビールをそこまで好きじゃない人も、ビールに詳しくない人も集まってランナー同士がつながっていく。
そういうところがビールを通じてつながっていくってことかなと思います。
ランニングだけじゃなくてサッカー、フットサル、音楽でも一杯の乾杯からひろがるつながりの可能性はたくさんあります。

美味しいビールと同時に生まれるモルト粕を資源として社会の中に循環させていく。そこには、地域を繋げる堆肥や世界に羽ばたくクラフトビールペーパー、人と人をつなぐ乾杯のストーリーがありました。あなたが魅力を感じた扉をぜひ叩いてみてください。わくわくするつながりがはじまりますよ。
*1 株式会社ペーパル https://www.pepal.co.jp/
*2 kitafuku https://kitafuku-project.com/