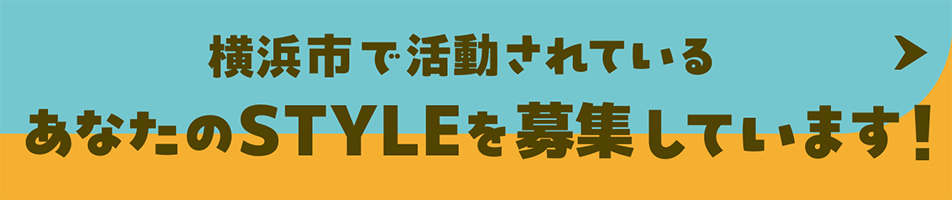動物達からいのちの循環を学ぼう
循環型経済 生物多様性
周りには広大に広がる緑地。その管理、間伐で伐採した竹は動物たちの餌に、そこから生まれる糞は堆肥として新しいいのちを育てる、そんな動物園があります。横浜市立金沢動物園。ここでは、資源をできる限り園のなかで循環させる仕組みづくりや、子どもたちと外来種のザリガニを捕獲し、ともにいのちについて学ぶ光景が広がっていました。動物園から里山や自然を元気にしていくいのちの循環のスタイルづくりとは。
動物も森も健康になる!?いのちと地球にやさしく、地域にひらいた動物園へ。
横浜市金沢区。京浜急行線金沢文庫駅からバスに揺られること約10分。広大な緑に囲まれた金沢動物園にたどり着きます。驚くべきはその立地です。じつは金沢動物園、約60万平方メートルという横浜市最大級の緑に囲まれた金沢自然公園の中にあるちょっと珍しい動物園。丘陵地を生かした広い園内は徒歩で一周するために約1時間30分かかるほど。草食獣を中心に約50種類の動物たちがのびのびと暮らし、日々いのちを紡いでいます。
1982年に開園した金沢動物園。20年ほど前からは金沢自然公園とともにその周りの自然環境に寄り添いつづけているといいますが、特筆すべきはその取り組みが動物を中心に資源を循環させているということ。森を荒廃させてしまう竹林の竹を伐採、その竹はゾウのおやつに。ゾウの糞は園内で堆肥にし、動物園の花壇へ。できる限り、園内とまわりの自然の中で循環させ、環境管理をする。動物園だからこそできる取り組みを模索するスタイル。そこに至った背景とはどんなものだったのでしょうか。飼育展示係長の須藤さんはこう話します。
須藤さん 金沢動物園は開園から約40年以上たつのですが、開園から約20年目の時に、再整備計画が持ち上がったんです。
この出来事がきっかけで、職員全員が、これからの環境の変化のなかで金沢動物園はどうあるべきかを考え始めたといいます。
須藤さん 横浜には3つの動物園がありますが、そのなかで金沢動物園はなにをするべきなんだろうと立ち返ったときに、もともとは里山だったこの広大な自然公園の資源を残しつつ生物多様性を守るサンクチュアリのような場所になることで、身近な生き物まで感じることのできる施設になったらいいのではという動物園全体の方向性にたどりつきました。

飼育展示係長の須藤一行さん。須藤さんの後ろに広がるのは、かつて竹林で埋め尽くされていたという園内の一部。竹の間伐により陽が地面まで入り新たな種が芽生える森に生まれ変わっています。
広大な自然公園の資源を残すために動物園としてなにができるのか。そんな模索のなか、竹林が急速に拡大し、他の木が減って周りの森が荒廃していくという課題に対して、ゾウのおやつとして竹林を伐採することで、森の保全に導いている取り組みも。そのはじまりについて、ゾウ担当の安藤さんは「じつは森の保全ではなく、ゾウのより豊かな暮らしを探究した結果、森が復活したんです。」と話します。

13年間、ゾウの担当をされている安藤正人さん。
安藤さん 10年ほど前から、アニマルウェルフェア*1の概念が動物園に浸透しはじめました。飼育されている動物がより豊かに、よりよい生活を送るにはどうしたらいいのかをしっかり考えていきましょうということです。その一環のなかで、飼育下のゾウの研究をしたところ、ゾウは野生と比べて行動のバリエーションが少ないことでストレスを感じていることがわかったんですね。
その原因のひとつにあげられるのが採食時間の長さだと安藤さん。野生のゾウが1日に数10kmも移動しながらその大半の時間を採食時間に費やしていることに対し、飼育下のゾウの採食時間は1回につき数分で終わってしまう。食べるという楽しい時間が終わると目的を持った行動が発現できず、結果ストレスにつながっているという研究結果だったそう。そこをいかに解決するのか模索がはじまったといいます。
安藤さん 餌を小分けにして何回もあげてみたりもしましたが、あまり効果が出ず。試行錯誤の末たどりついた手段が竹の給餌でした。竹は割らなければ食べることができず、またゾウは竹の内側を好んで食べるため時間もかかります。なおかつ、嗜好性が高くよく食べてくれる。そしてカロリーも低い、なかなか理想的な餌なんですね。そこで積極的に竹の給餌をしたところ、ストレスがどんどん軽減していく結果を得ることができました。ゾウにより豊かにもっと楽しく暮らしてほしいという思いから始まった竹の給餌が、周囲の山々を荒廃させつつあった竹林を伐採するという行為につながり、さらに里山の再整備につながったんですね。かつて生業として人が竹をとっていた時代と同じように、必要だから竹を取り森が保全されるという循環がゾウがいるおかげで実現できている。それが金沢動物園のゾウと竹の関係なんです。

竹の給餌風景。1日の食事量は約300kgというオスのボン。竹は1日10本ほど食べるそうです。

こちらはメスのヨーコ。太い竹もバキバキと折って食べます。その光景は圧巻!
ゾウの給餌時間を伸ばすために竹を地域の里山から調達する。ストレス軽減の研究結果が明確になった3年前から本格的に竹の給餌がはじまったといいますが、すでに3か所の荒廃した竹林が整理され、結果、山の環境の改善につながっています。
さらにもうひとつ、地域の廃棄物を生かしたユニークな取り組みについても教えてくれました。

インドゾウ担当・上夏井あずささん
上夏井さん 約5年前から市内でコーヒーの焙煎や商品の製造、カフェ事業などを手がける三本珈琲株式会社よりコーヒーの生豆を煎った際にでる食品残渣をご提供いただき、ゾウの寝床に混ぜて使用しています。
本来は廃棄物扱いになってしまうコーヒー豆の食品残渣ですが、ゾウの寝床につかうことでさまざまな効果も。

ゾウ舎内、おがくずとコーヒー豆の食品残渣を混ぜたゾウの寝床。まったくといっていいほど臭いはしません。
上夏井さん 混ぜることで吸水性が向上し、消臭効果も生まれています。また、ジャングルの生き物なのでコンクリートで痛みがちな足の裏のケアにもなっています。なにより、ゾウたちが心地よく過ごせていることが嬉しいですね。
動物たちがより豊かに暮らすために。その思いから生まれたアクションがさまざまな形でつながり循環が生まれる、それがいまの金沢動物園です。

竹を食べたゾウの糞は園内にて堆肥にし、花の肥料などに活用。
金沢自然公園内の菜の花畑の他、山手西洋館、長浜公園など市内公園にも活用しています。
ゾウ以外の動物たちも竹の葉を食べたり、園内の管理で伐採した木々は動物たちの遊具になったりと園内外の資源を循環させることで動物もひとも心地よさを感じることのできる金沢動物園。
堆肥の取り組みや園内の木々の整備後活用法など、ひとつひとつの取り組みは決して大きな規模ではないといいますが、動物を中心に金沢自然公園という広大な森、山を保全し次世代まで残す。そこにはいのち、そして持続可能な環境づくりに本気で向き合う、そんな強い意思を感じるお話でした。
地域の子どもたちと自然を守りいのちを学ぶ動物園へ。
金沢自然公園というかつては里山だった地域に内包された金沢動物園。さらに地域に開いたその先の取り組みも動きはじめています。金沢自然公園にあるみずの谷にて水生生物の調査や保全をおこなう市民参加型の「ザリガニ調査」です。

教育普及・身近ないきもの館担当 先崎優さん
先崎さん ザリガニの捕獲調査は昨年の6月からはじまりました。もともと外来種の対応をするなかで年に一回ほどは防除作業をやっていたんですが、追いついていないという状況でした。同時に金沢動物園に訪れる子どもたちとフィールドに出ていっしょに学べるような取り組みを模索していたこともあり、毎月1回ザリガニ調査を市民といっしょに実施する取り組みがスタートしました。実施することで、月ごとの変化も見えてくるのでモニタリングをして、より効率的に防除作業を進めるいうことにもつながっています。
ザリガニ調査の実施スタンスとしてはまず安全確認からはじまり、その後生き物を捕獲、種類ごとに分別してそのつどの気づきをフィードバックするスタイルです。地元の大学生もボランティアで参加してくれていて多様性のある地域コミュニティに開いた活動にもつながっています。

毎月第4日曜日14時に金沢自然公園内の池、みずの谷にて実施している生き物調査。防水パンツなど本格的な装備もみな持参してくるそう。参加条件を記載したポスターなどでの告知に毎回20名ほどの大人や子どもたちが集まり調査しています。
先崎さん 調査がはじまり、まずリピーターがとても多いことに驚きました。フィールドにでて子どもに生き物のことを学んでほしいと思ってもどこでできるかわからないという方も参加してくれています。そういう方の入り口の部分をつくっていくこともこれからの動物園の意義なのではと感じています。
ゆくゆくはもっと敷居を下げて、毎月第4日曜日に自然公園にいったら動物に詳しいおじさんがいていっしょになにかできるよ、という里山の風景の一部のような企画になればいいなと思っています。
やはりいま、子どもたちが生き物に触れ合う体験は少なくなっていると思っていて、フィールドでザリガニやメダカなどに直接触れた野遊びのような原体験が心の中にあると、参加した子どもたちが成長したときに、金沢のあの森をこれからも守っていきたいと思うそのきっかけにつながればいいですよね。

リピーターの吉澤宏海さん(5歳)。小さなころから金沢動物園に通っているそう。「いつも参加していて楽しいです。またやりたい!」と笑顔。
ザリガニ調査は単に外来種を防除することを伝える取り組みではないと先崎さんは続けます。

メダカやエビなども捕獲。在来種、外来種に分別してデータをとります。最近では在来種の個体数も増えてきたそう。調査開始当初は毎回50匹ほどいたザリガニも今回の調査では小さな個体が数匹という結果に。※季節変化もあり。
先崎さん 防除作業はメディアでも目にする人気のあるコンテンツではありますが、映像だけみていると、そこでのいのちの扱いが適切ではない場合もあり、本当にそれで良いのかという疑念もあります。そもそも外来種は人がきっかけで入ってくることが多く、生き物自体に良い、悪いはありませんよね。
ただ、より良い生物多様性、持続可能な環境を目指す上で防除はやはり必要な作業になるので、ちゃんといのちと向き合って丁寧に扱いましょう、外来種が悪いわけではなくひとにも責任があるよね、ということは作業を通じて伝えていますし、大切にしていることです。
動物園といういのちを扱う場所だからこそ、発信できることがある。ザリガニ調査という入り口から地域とつながり、金沢の自然のなかで子どもたちと学び育む場へ。金沢動物園の地域に開いた入り口づくりから未来の里山の担い手が育っている、そう感じました。
見て楽しむだけじゃない、地域のいのちの循環を生み出す存在に。
金沢自然公園という広大な緑に抱かれた動物園としてどうあるべきか。そんな課題からはじまった金沢動物園の地域とともに循環するスタイルづくり。
これから先、どんな未来を見つめているのでしょうか。

展示飼育係 野口忠孝さん。動物園の業務に加えて園内外の緑の整備やもともと里山に多く自生していた植物の保全なども行っているそう。
野口さん ここはもともと里山環境だった場所を整備してできた自然公園です。
40年という月日がたち環境が崩れはじめているなかで、もとの里山に近づけるような取り組みを動物園として続けていくことが大事だと思っています。
まだ準備段階ですが、動物の飼育をしている部屋を園内の整備で伐採した薪で温めるための薪ボイラーを導入する予定です。里山の間伐材も有効活用できれば、エネルギーの循環も園内でできるようになる。増えすぎてしまった常緑樹を切り、徐々に落葉樹林が多い環境に戻しつつ、切った木は薪からエネルギーへ。すると、30年、40年先も里山の環境を整備し守りながら、動物園の動物も豊かに暮らしていけるということです。

かつて人が竹を必要とし森が守られていたように。ゾウが食べることで森は再生しつづけます。
安藤さん ゾウのよりよい暮らしを考えつづけた結果が里山保全やさまざまな循環に波及してきました。お客様にも「じつは海外からきたこのゾウが里山の竹林を食べていて、この周りの森を守っているんです」とお伝えすることでこの里山保全の気づきにもつながっているのかなと思います。ゾウが地域の里山の資源を利用していることで、50年後、100年後、このエリアの生物多様性が守られていたら理想的ですよね。100年先まで役にたてるような施設、この地域にゾウがいて、動物園があってよかったと感じてもらえる、そんな金沢動物園でありたいと思います。

いのちと向き合い、ともに学ぶ。
動物たちとともに守り、伝えていく金沢動物園スタイルづくり。
動物たちがいるからこそ、いのちの循環のなかに持続可能な環境づくりを取り入れて、チャレンジする、金沢動物園にしかできない挑戦はまだまだ続いていきそうです。
まずは金沢動物園、訪れてみませんか?さまざまな入り口はもう開いていますよ。
アニマルウェルフェア*1
飼育動物をストレスや病気などの苦痛から解放するという考え方です。そのためには、清潔な環境の提供や適正な給水・給餌だけではなく、動物種に応じた適切な広さの飼育スペースを確保したり、本来の運動能力を発揮できるようにすること、隠れたい時に隠れられるような展示場にすることなどが必要となります。
(尚、本記載は横浜市ホームページの「野毛山動物園リニューアルプラン」内にて記載のアニマルウェルフェアの説明文になります。)
※水生生物は水から上げる時間を極力短くし、アニマルウェルフェアに配慮して撮影しています。
【情報】
金沢動物園
住所:〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東5丁目15−1
電話:045-783-9100
時間:9:30~16:30(入園は16:00まで)
休館:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、12/29~1/1、5月・10月無休
ホームページ:https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/