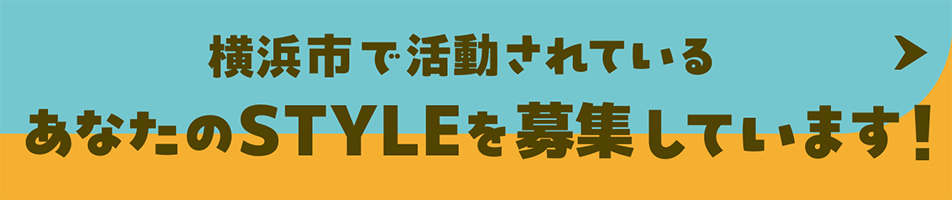アートの力で社会課題を学ぼう
再使用エネルギー 循環型経済 生物多様性

この記事の目次
子どもたちにとって体感的な理解が難しい「SDGs」の概念。しかし、地球温暖化や紛争・貧困など多くの社会課題は他人事ではなく、誰もが向き合うべきものです。そこで、アート作品の制作を通してこのテーマを“自分事”として捉えてもらおうという、ユニークなプロジェクトが展開されています。
その仕掛け人は、アート教育団体『EduArt(エデュアート)』。横浜市を拠点に、公立の小中学校や高校で特別授業を展開しています。某日、横浜市立みなとみらい本町小学校3年生の総合学習の授業として、そんなEduArtの活動が行われました。

横浜市立みなとみらい本町小学校は、学校全体でSDGsの学びに力を入れています。
頭や言葉ではなく、体を使って考えたことが学びの経験値になる
『WASTE NO FOOD ~アートで考えるフードロスのこと~』(以下:WASTE NO FOOD)は、児童がフードロスについて学び、その学びをアート作品として社会に発信するEduArtのプログラムです。ちなみにこれは6月14日(土)にJR横浜タワーで開催されたフードドライブ活動『FOOD for ALL YOKOHAMA』と連動した取り組みとして企画されたもの。このプログラムで児童たちはフードロス啓発のポスターを作成し、完成した作品はFOOD for ALL YOKOHAMAの会場内で掲示されました。
子どもたちにアート作りを通じて社会課題を考えてもらうことに、どのような意義を感じているのか。代表の望月実音子さんと副代表の野村麻友さんのお二人に、EduArtが発足した背景や大切にしている考えについてお聞きしました。

EduArt副代表の野村麻友さん(左)と代表の望月実音子さん(右)。
望月さんがEduArtを立ち上げたのは、何がきっかけだったのでしょうか。
望月さん:現在の造形教育や図工教育というものが、技術に偏っているのではないかという懸念からです。4〜5歳くらいまでは本当に自由に表現していた子どもたちが、やがて巧拙を気にして苦手意識を持ってしまうのは、クリエイティビティではなく技術にフォーカスした教育に一因があるような気がしています。既存の価値観ではクリアできない課題が山積している今の時代には、ゼロをイチにする発想や、違う視点でものを見ることが求められていると思っています。そうした中で、クリエイティビティにアプローチした美術の教育が、今の日本に必要なんじゃないかなと強く感じています。
アメリカやオランダなど、海外で暮らした経験も豊富な望月さん。日本と海外との違いについては、どのように感じているのか尋ねてみました。
望月さん:例えば、日本の子どもたちはみんな折り紙が上手ですが、海外の子どもたちは意外とできないんです。説明通りに正しく制作できるのはひとつのスキルですが、一方でプロセスを指示されないと作品づくりが進まない傾向があると感じています。
社会課題をテーマにしたプログラムを小学校で行うようになったのは、なぜなのでしょうか。
望月さん:多様性が重視される現代の社会において、社会課題を解決するにはマイノリティ側ではなくマジョリティ側の意識の変化が必要だと感じています。多様性による恩恵は社会全体で享受されるはずですから。では、どう変えていけばいいんだろうと考えたときに、やはり教育現場がふさわしいのではと。社会を変えていくためには子どもたちの教育こそ一番の近道で、そこしかないと思いました。

「小学校3〜4年生の子どもがこの時期に社会課題を学ぶことは、倫理観の育成にもつながる」と望月さん。
アート制作を取り入れたプログラムを実施している理由について、望月さんは次のように語ります。
望月さん:アート制作には、学びを“体感”として落とし込む作用があると思っています。手を動かしながら、自分が向き合っているテーマやコンセプトを作品にする行為は、考えながらものを作る、あるいは作りながら考えるといった、学びを深めるためのプロセスだと捉えています。本を読んだり、言葉で教えてもらったりする方法では得られない体感的な学びとして、子どもたちの記憶に残るのではないでしょうか。
子どもたちが社会課題を自分事として考え、広く発信し、社会の一員である意識を育んでいくのがEduArtの目指すところ。そのために、プログラムではどんなことを大切にしているのでしょうか。
望月さん:自分の声が届いたという実感ですね。きちんと話を聞いてくれる大人がいたとか、ちゃんと届ける場所があったとか、そういった成功体験の積み重ねが「自分で社会を変えられるんだ」という自信につながると思うんです。
野村さん:明るく前向きなメッセージで終われるように気をつけてプログラムを作っています。自己肯定感が低く、未来に夢がないといった状況を変える一助になりたい。授業後はいつも望月さんと「未来は明るいね」と言いながら帰っています。

「アートには絶対的な正解がないから、子供たちが自ら答えを見つけていける」という望月さんの考えに共感し、EduArtに加わった野村さん。
『WASTE NO FOOD』〜アートで考えるフードロスのこと〜
ここからはみなとみらい本町小学校で開催された『WASTE NO FOOD』の授業風景についてお伝えしましょう。
児童たちが集まったのは図工室。まだ何をやるのか分からないこともあってソワソワした様子です。
まず望月さんは、フードロスという社会課題をクイズ形式で紹介し、児童たちの関心を引きつけます。「Aだと思う人?」「じゃあ、Bだと思う人は?」と問いかけると、元気な声と共にたくさんの手があがりました。

みんな興味津々で、楽しそうに授業に参加しています。
フードロスって何が問題なんだと思う?と子どもたちに望月さんが問いかけると、もったいない以外にも「地球温暖化になってしまう」といった、フードロスの増加によってもたらされる具体的な問題を挙げる児童もいて、思わず感心させられました。

恐れずに自分の意見を話す児童たちを、担任の先生も見守っています。
児童たちに「自分たちにできることは何か」と問いかけると、「フードロスをしないよう、まわりに伝える」といった前向きなアイデアが返ってきました。そこで、いよいよポスター制作の説明へ。今回は、雑誌やチラシを切り抜いて素材を集め、それらを組み合わせて表現する、コラージュという技法でポスターを制作します。

材料は食べ物の写真や文字を大きく印刷した素材、食品のチラシ、新聞記事、雑誌など。

「食べ残しは燃やされて全部なくなってしまうと聞いたので、CO2の煙をイメージしました」と、素材選びにも独創性が光ります。
果物をきれいに切り抜いて左右対称に並べた作品や、文字の配置に凝った作品、恐竜や魚の写真が並んだ作品、中にはベース紙からはみ出してレイアウトする児童もいるなど、それぞれの感性で自由にポスターを制作していきます。
最後は、みんなで完成したポスターを見せ合い、それぞれが作品に込めた想いを発表しました。

大好きなお肉を無駄にしないという気持ちが素直に表れたポスターに、みんなも笑顔です。
授業を終えた児童たちに作品のコンセプトや工夫などを聞くと下記のように答えてくれました。
「世界にはご飯を食べられない人たちがいることを、スープやおかずの切り抜きや『助けてください!』という言葉で表しました」
「ポスターはごみの色をイメージして、ご飯がいっぱい捨てられているのを表すために、色合いを工夫しました」

「酸っぱいものや苦手な果物でも、工夫してジュースに変えるとフードロスがなくなると思ってこの作品を作りました」とアイデア満載のコメントも。
さらに、授業を通してフードロスについてどのように感じたかも児童たちに聞いてみました。
「自分が食べきれる量をきちんと考えて、残さず食べようと思いました」
「苦手なものでも好きなものと一緒に食べることで残さずに食べれるかもしれないと思いました。こうやって工夫することで全部食べるようにしたいです」

「いつも朝ご飯とかで好き嫌いをしちゃってたけど、このポスターを作って、苦手なものも頑張って食べようかなって思いました」
授業の様子をFOOD for ALL YOKOHAMAの主催団体である『YOKOHAMA Station City運営協議会』(以下:YOKOHAMA Station City)の今井翔太郎さんが見守っていました。
ちなみにYOKOHAMA Station Cityは、JR東日本グループ10社から成る組織で、JR横浜駅周辺のタウンマネジメントや情報発信に力を入れています。
今井さん:YOKOHAMA Station Cityでは、2022年から横浜市の皆さんとフードドライブに取り組んでいます。いろいろな方とご一緒に活動を広めていきたいと思い、EduArtさんにお声がけしました。
授業を見学した感想について今井さんは次のように語ります。
今井さん:児童たちの純粋さや率直さが印象的でした。彼らが発信した社会課題を、大人たちにも自分事にしてもらえるよう、我々のイベントを通じて、より広く伝えていきたいですね。そこから、みんなで未来をより良くしていこうとする輪が広がっていくのを期待しています。

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 地域共創部の今井翔太郎さん。
大勢の人々の目に触れる会場にポスターが飾られると知らされた児童たちは、喜んだり、少し恥ずかしがったり。そんな様子を見て、望月さんはこう語ります。
望月さん:みんなクリエイティブだし、すごく可能性がありますよね。また、そこを評価してあげる大人がいることで、より発展していくと思うんです。それが親でも先生でもなく、私たちのような外部の人であるというのも、関係性としてすごく良いのではないかと考えています。児童たちをたくさんの人が応援してくれたらいいなと思います。
作品は横浜駅でお披露目、街ゆく人の会話のきっかけに
子どもたちが制作したポスターがお披露目された『FOOD for ALL YOKOHAMA』の展示会場(JR横浜タワー)では、通りすがりの人がポスター作りに参加できるワークショップも行われ、授業に参加した児童たちをはじめ、たくさんの親子が足を止め、フードロスについて話し合う様子が印象的でした。

授業と同じように、コラージュでポスター作りができるワークショップの様子。

会場にはみなとみらい本町小学校で授業を受けた児童と先生の姿も。
当日の会場では、家庭で余っている食品を寄付してもらい、必要な人に届けるフードドライブも実施。寄付してくれる人はもちろん、立ち止まって取り組みについて質問する方も、それぞれにフードロスという社会課題に触れる機会となっていました。

児童たちのポスターが飾られた会場では、誰でも参加できるフードドライブを実施。
子どもたちの当事者意識とクリエイティブが、未来を変える
このほかにも、EduArtではさまざまなプログラムを展開しています。SGDsの17の項目をスクエア型の工作で表現したり、水の大切さや循環を学ぶペインティングをしたり、オリジナルの「トピックカード」で社会課題を学んだり。高校生向けには、人権をテーマにインスタレーション制作に挑む授業も手がけ、多くの児童・生徒たちがアートを通じて社会課題と向き合う機会を作っています。
大人に比べて人生経験の少ない児童たちは、自由な発想力を持つ一方で、世の中に数多く存在する社会課題を見極める力はまだ発展途上にあります。今回のプログラムを通じて彼らが得た大きな学びは、フードロスをはじめ、自分たちの生きる社会には解決しなければいけない課題が多く存在することです。そして、課題解決の近道は、一人一人が主体的に向き合い、具体的なアクションを起こす——そんな気づきだったのかもしれません。
民間企業、NPO法人、そして教育機関が一体に。アートというアプローチが横串となって間をつないでいます。EduArtの挑戦はこれからも続き、子どもたちの創造性や当事者意識に、周りの大人がハッと気づかされることも多くあるはずです。
【情報】
EduArt
https://www.eduart.jp/
YOKOHAMA Station City
https://yokohamastationcity.com/