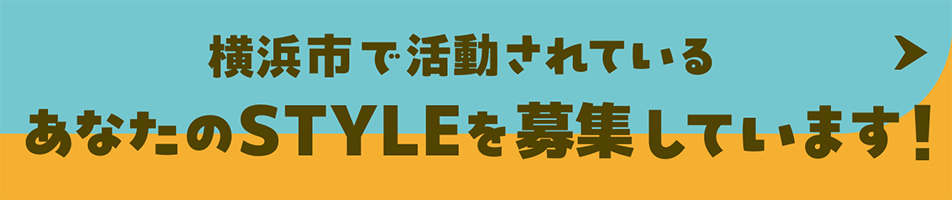大切なお花を長く楽しもう
循環型経済

この記事の目次
横浜市では、地球にやさしい暮らしにつながるさまざまな人やアクションを「地球1個分で暮らそうSTYLE100」で紹介しています。今回は、SDGsに関する記事も多数発信する雑誌「Hanako」と、横浜出身のフローリスト・前田有紀さんと共に、年間10億本もの花が廃棄されているという「フラワーロス」問題に着目。前田さんが日常的に実践していることを伺いながら、誰でも自宅ですぐにトライできるアクションを考えました。
横浜というまちが、
自然を愛する心を育んでくれた。
アナウンサーからフローリストに転身し、花とのサステナブルな付き合い方を提案している前田有紀さん。自然豊かな横浜市で生まれ育ち、花や緑に触れる子ども時代を過ごしたといいます。しかしテレビ局に入社してからは生活が一変。都心のビル群に囲まれ、ただひたすらに走り続ける毎日。時折、無性に自然が恋しくなることもあったのだそうです。
前田さん:入社5年目にようやく心に余裕が生まれ、部屋に花を飾るようになりました。すると、それまで寝に帰るだけだった家が豊かな場所に変わったんです。改めて、私は花が好きなんだと実感しました。花に触れている時の自分が一番“らしく”いられているんだなって。
花に関わる仕事がしたいと、10年勤めたテレビ局を退社し渡英。コッツウォルズの古城で見習いガーデナーとして働いた経験が、価値観を変えるきっかけになったといいます。
前田さん:コッツウォルズで暮らす人々は、生活の中に花を取り入れるのがとても上手。ルールにとらわれず、自由な楽しみ方をしている姿が印象的でした。実はお花やガーデニングって、どちらかというと年配の女性が楽しむもののようなイメージがあったんです。でも決してそうではなくて、年齢も性別も関係なく、全ての人に豊かさをもたらしてくれるものだと気づかされました。
横浜のまちで育んだ花への思いが、コッツウォルズでより鮮やかに。帰国後、前田さんはフローリストとしての道を歩み始めます。

愛おしそうに花に触れる前田さん。
現在は鎌倉の一軒家で家族とともに暮らす前田さん。自身が営むフラワーショップで売れ残った花を自宅に持ち帰ることも多く、フラワーロスの課題に日々直面していると話します。
前田さん:仕入れから時間が経った花は、買っていただいてもすぐに枯れてしまうので、たとえ綺麗だとしても販売することができません。結婚式などのお祝い事に使われる花も同じ。短時間で役目を終えるため、まだ美しくても廃棄されてしまうことが多いんです。
私たちも普段の生活の中で、お祝いのブーケをもらうことがきっとあるはず。大切な思いが込められた花だからこそ、できる限り長く楽しみたいもの。ちょっとした工夫をして、フラワーロスの削減を目指しましょう。
大切な花を使い捨てないために。
プロがすすめる「ドライフラワー」の作り方。
まず実践したいのが「ドライフラワー」です。ただ一つ注意しておきたいのは、ドライフラワーに適した花と、そうでない花があるということ。その基準は?
前田さん:ポイントは水分量。水分を多く含んだ花は乾燥に時間がかかり、カビも生えやすくなります。花びらが薄いものも形を保ちにくいので不向き。例えば、カラーやランなどの南国の花は、水分量が多く繊細なのでドライフラワーには向きません。逆に向いているのは、ワイルドフラワーと呼ばれる植物。オーストラリアや南アフリカなどの乾燥地帯に自生するため、水分量が少なく、生命力の強さが特徴です。

ドライフラワーに適したワイルドフラワーたち。左からユーカリ、カンガルーポー、エリンジウム、グレビレア。
また同じ花でも、季節によってドライフラワーにできる場合とできない場合があるといいます。
前田さん:例えば、アジサイは梅雨時期に咲いたものだと乾燥しにくいため、水分量の少ない真夏から初秋にかけてのものがベターです。ただこうした判断はある程度の知識がないと難しいので、まずは葉物から挑戦してみたり、何となく水分が少なそうかな?くらいの基準でやってみるといいと思います。
吊るすだけだから簡単。
「ハンギング法」にトライ!
ドライフラワーの作り方はいくつかありますが、最も手軽にできるのが「ハンギング法」。ドライにしたい花を麻ひもなどでしばり、風通しのいい場所に吊るしておくだけでOKです。吊るす上で気をつけることは?
前田さん:いただきもののブーケをドライフラワーにする場合、いろいろな花が一緒に束ねられているので、一度分解してドライに向いていそうなものだけをピックアップすると失敗が少ないです。早めに吊るした方が形と色を保ちやすいですが、生花の状態を長く楽しみたいなら、10日くらい飾った後にドライにしてもいいと思います。特に正解はないので、優先度に応じて吊るすタイミングを決めてください。

直射日光が当たらない場所に吊るすと色が抜けにくいそう。
一輪ずつ吊るしておくだけでも絵になりますが、一度分解したものを、束ね直してスワッグ(壁飾り)の状態にして吊るすのも素敵です。スワッグにする際のコツは?
前田さん:まず葉物でベースを作ってから、顔になる花を加えるのがいいと思います。さらに長さの違うものを段違いに重ねると、全体の形を整えやすいです。手元で束ねているだけだとバランスがわかりづらいので、少し自分から離して、逆さにした状態を確認しながら調整していくのもポイント。あとこれは好みにもよりますが、形の違う花を組み合わせると、少ない本数でもにぎやかに見えます。

麻ひもでしばった後は、お好みのリボンなどで自分流にアレンジ。
スワッグのドライフラワーは、生花のブーケを楽しむのと同じ感覚で、乾燥していく過程でも空間を彩ってくれるという利点があります。前田さんは普段、どんなふうにドライフラワーを飾っているのでしょうか。
前田さん:息子たちが描いた絵などを飾る壁があって、そこに一緒に掛けることが多いですね。いつも花が身近にあるので、息子たちも花の名前に詳しくなりました。「これ、チューリップでしょ?」という感じで、得意げに言ってきます(笑)。

白壁に映える、まだ青々とした状態のスワッグ。
自宅でのドライフラワー作りの醍醐味は「自由さ」にあると話す前田さん。
前田さん:上手にできるかを気にしすぎて、楽しめなくなってしまったらもったいないですよね。わからなければ、とりあえず全種類を乾燥させてみるのも全然アリだと思います。うまくいかなかったら次に活かせばいいわけですし。失敗も含めて楽しむくらいのおおらかな気持ちで向き合った方が、花のある生活を続けやすいと思います。

「このユーカリは、ドライにする過程で葉っぱが少しいびつになっちゃいましたけど、オブジェっぽくて私は好きです」と前田さん。
形を変えても、長くお花を活用する。
「土に還す」という選択肢。
ではブーケの中の、ドライフラワーにしづらい花はどうすればいいのでしょうか。前田さんが実践しているのは「土に還す」という方法です。
前田さん:うちには常に花がありますが、可燃ゴミとして捨てたことは一度もありません。しおれたら庭やコンポストの土に混ぜて、虫や微生物に分解してもらっているからです。この方法を取り入れてから、庭に栄養が行き渡るようになって土が肥えました。

前田さんは、自宅の庭の一角にコンポストを設置。できた堆肥は野菜栽培に活用している。
以前は虫が苦手だったという前田さんですが、花を土に還すようになって、虫も循環を担う一員だと思うようになったそうです。
前田さん:ダンゴムシ、ヘビ、トカゲ、フクロウなど、さまざまな生き物の連鎖でこの自然は成り立っています。私はそこに住まわせてもらっているんだと考えると、虫への苦手意識が少しやわらぎました。もちろん、今でも急に飛んできたりすると「わ!」って声が出ちゃいますけど(笑)。
実は今日からすぐできる!
前田さん流、土への還し方。
「土に還す」と聞くと難しく感じますが、方法はとてもシンプル。花びらや葉、茎を細かく切って、土の中にザクッと埋めるだけです。自宅に庭がない場合でも、プランターの土などで代用できます。

細かく切れば切るほど土に還りやすいのだとか。
太めの枝は「地面に挿す」のが前田さんのこだわり。雨水が枝を伝って土の中に入ることで、分解が早まるのだそうです。
前田さん:枝を挿すと雨水が浸透しやすくなって、下の土が驚くほどやわらかくなるんです。有機農法を取り入れている農家さんの畑でも、こんなふうに枝が挿さっている光景をよく目にします。枝の間に落ち葉などをねじ込んでおくと、さらに分解が進みますよ。

挿す時はグッと強めに。「ベランダ菜園をされている方にもオススメ」と前田さん。
「土に還す」という方法を使えば、 生花だけでなく飾り終えたドライフラワーもゴミにせずに済みます。
前田さん:フラワーロスを減らす目的もありますが、土がどんどんよくなっていくことを実感できるので、花を見て楽しむのとはまた違った充実感を味わえますよ。
ベランダで使える小ぶりなものも。
コンポストを活用してみよう。
3年ほど前から、家で出る生ゴミは全て庭のコンポストで処理しているという前田さん。
前田さん:始める前はコンポストって難しそうなイメージがあって、私にできるのか少し不安でした。でもやってみると意外と簡単で。特に気温の高い夏は分解が早く、中に入れた生ゴミや花は5日ほどで姿が見えなくなってしまうんです。

事前に花を切っておくのが手間な場合は、スコップで細かくしながら混ぜてもOK。
前田さんのお宅のように庭にコンポストを設置できなくても、ベランダで手軽に使えるコンパクトな商品が販売されているので安心です。
前田さん:自宅で分解できるものを、わざわざゴミ袋に入れて遠くまで運んで燃やす必要なんてないですよね。息子たちも土遊びの一環で野菜の皮や花をコンポストに入れています。日常生活の中で当たり前のように循環を知ることができるのも、コンポストのいいところだと思います。

ベランダでも使える小ぶりな不織布コンポスト。「このサイズなら場所を取らなくていいですね」。
家族で楽しみながらサステナブルな暮らしを実践している前田さん。今後、どんなふうに花と向き合っていこうと考えているのでしょうか。
前田さん:最近は日本でも「スローフラワー」という言葉が少しずつ浸透してきました。これは「スローフード」と似ていて、農薬や化学肥料を使わず、種から育てた季節の花を、その土地に住む人が飾って楽しむという考え方です。私が経営している鎌倉のお店でも、神奈川近郊で育った旬のオーガニックフラワーを取り扱っています。まだまだ小さな一歩ではありますが、花に携わる人間として、環境に負荷をかけない選択肢を広く提案していけたらいいなと思っています。
贈り主の思いが詰まったブーケをドライフラワーにして長く楽しみ、土に還して豊かな日々を循環させる。日常で取り入れられる小さな一歩が、フラワーロスを解決する大きなアクションとして花開いていくことでしょう。
【情報】
・Hanako webより転載