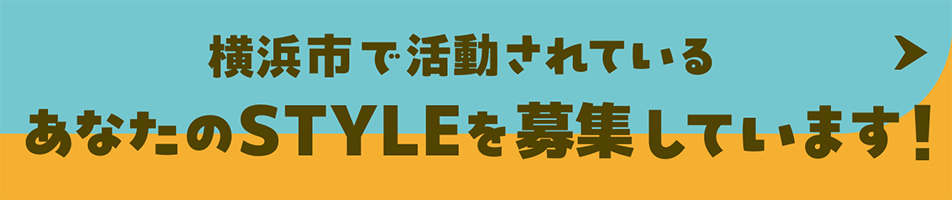地球にやさしいフェスをひらこう!
再使用エネルギー 循環型経済
この記事の目次
横浜から発信する、新たなフェス体験の形。2025年4月、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』(以下『CENTRAL』)が初開催されました。『横浜赤レンガ倉庫』や『Kアリーナ横浜』など、横浜の象徴的な複数拠点を舞台に、音楽とサステナビリティが融合する新体験が幕を開けています。
1日に数万人が集う音楽フェスは多くの人々が熱狂する一方で、その裏側では大量のゴミ、エネルギー消費、移動によるCO2排出など、環境への負荷が課題となっています。こうした状況に対し、近年では『FUJI ROCK FESTIVAL』をはじめとする国内外の野外フェスにおいて、ゴミの分別・リサイクルの徹底、再生可能エネルギーの導入など、環境負荷を低減するさまざまなアイデアでサステナビリティを追求しています。
『CENTRAL』もそうした新たな潮流の中に位置づけられますが、他の音楽フェスと異なるのは、『リソースハブ』という独自の取り組みを打ち出している点です。『臨港パーク』の入場無料エリアに設置されたゴミ回収ステーション『リソースハブ』は、来場者にとって不要になったものが、分別という協力を経て新たな資源へと生まれ変わることを目指す場所です。さらに、分別に協力した人には、まだ美しく咲いているにもかかわらず廃棄されてしまうロスフラワーのポット苗が贈られるという、心温まる仕掛けも用意されています。
この『リソースハブ』には、どのような思いが込められているのでしょうか。そして、来場者はこの取り組みにどのように反応するのでしょうか。音楽の祭典を楽しみながら、持続可能な未来へと貢献する『CENTRAL』の挑戦に迫ります。
商業的な成功だけじゃなく、世の中に意味のあるフェスを。
音楽フェスという大きなイベントで、いかに環境負荷を抑えながら、思いっきり楽しめる場を生み出せるのか。それを実現するために奮闘した、ソニーミュージックグループを中心とするCENTRAL実行委員会のお二人にお話を伺いました。

CENTRAL実行委員会の佐藤勝好さん(左)と矢澤ゆりさん(右)
そもそも『CENTRAL』では、なぜサステナブルを大事にしようと思い立ったのでしょうか。
佐藤さん:今回PRとサステナブルの取り組みを担当しているプロジェクトリーダーが、オランダの『DGTL(デジタル)』というサステナビリティを実装した音楽フェスを知り、これこそ今取り組むべきことだと強い意識を持つようになったんです。
佐藤さん:我々としても、『CENTRAL』で単に商業的な成功だけを収めればいいとは全く思っていなかったんですね。フェスが乱立している時代に新しく立ち上げるのであれば、何か世の中に対して意味のあることをやらなければ、という思いがずっとありました。けれども、なかなかその答えが見つかっていなかったのです。そのような中で、サステナブルは本当に大切なことだと彼が力説してくれて、確かにそうだなと。探していた答えに向かって、イメージが一気に広がりました。
ゴミ回収ステーション『リソースハブ』のアイデアも、その思いを軸にして生まれたといいます。『リソースハブ』のユニークな点は、来場者が自らゴミを捨てるのではなく、サービスカウンターのような受付でゴミを手渡し、受け取ったスタッフが分別して捨てること。着想源は『DGTL』にあったものの、オランダのそれとは全く異なる日本らしいものになったと二人は話します。
矢澤さん:オランダは国として環境意識が高いこともあってか、そもそもサステナブルな行いは合理的だという考えがベースにあるように感じています。一方で、日本で展開した『リソースハブ』は、人とコミュニケーションを取りながら良いことをしたという実感や、やり取りをする場所があったことが嬉しさにつながるような、より人の思いが通うような場所になっていたのではないかと思います。
佐藤さん:我々のコンセプトとして「日本の響きを世界へ」というものがあります。日本らしいサステナブルとは何か、ということを私も意識していました。オランダの事例を参考にしつつ、歴史や文化も全く違う我々にとって、何がサステナブルと明確に言えるのだろうかと考えた結果、今回の『リソースハブ』のあり方につながったと思います。
実際にやってみて、来場者やスタッフから嬉しい言葉もありました。
矢澤さん:来場者の方に「これは何の取り組みなんですか?」と興味を持っていただき、ゴミを捨てることへの意識が変わっているように思えて嬉しかったです。全国から集まったボランティアの学生も、環境への意識は持っているものの、自分たちが動けるような場所がないと感じていたそうで、今回がぴったりの機会だったと言ってくださる方がいました。ご覧になった横浜市の方からは、サステナビリティの活動でご一緒するモデルケースになったのではないかとお話をいただき、そのような場を提供できたことが良かったと感じています。

『リソースハブ』を設置した臨港パークの『CENTRAL FIELD』
「指導ではなく、共に楽しむ」リソースハブが育むもの。
『リソースハブ』を形にするためにプロジェクトに加わった、株式会社博展と『ごみの学校』。その中心人物として携わったお二人にも、企画当初から振り返っていただきました。
白川さん:私たちは昨年『DGTL』の視察に行かせていただき、その内容をさまざまな場所で発信していました。それをソニーミュージックグループの方がたまたま見つけてくださり、日本でそのような取り組みを行うのであれば、ぜひ一緒にできないかとお声がけいただいたのが始まりです。
そして『CENTRAL』の話が上がり、『リソースハブ』の企画がスタートしたといいます。
白川さん:博展が音楽フェスのゴミステーションを運営するのは今回が初めて。そこで、『ごみの学校』さんに運営支援をしていただくことで、より精度の高い分別ができるのではないかと考えたのです。

株式会社博展で、サステナビリティ関連のプロジェクトに多く携わっている白川陽一さん
『ごみの学校』はゴミについて学べるコミュニティとして2021年2月に誕生し、今では企業や自治体の相談役としても幅広く活動しています。
寺井さん:もともと私は、廃棄物処理会社で新卒からずっと働いていました。その中で、分別がされていない、リサイクルできるものがどんどん捨てられていく現実をずっと見てきたんです。どう分別すればリサイクルできるのか、ゴミの世界にいる立場として世の中に発信していかなければと、みんなで学べる場を作ろうと思ったのが『ごみの学校』設立のきっかけです。

『ごみの学校』代表の寺井正幸さん
企画を進めていく過程で、重視したのはどのような点でしょうか。
白川さん:『CENTRAL』というフェスの雰囲気にしっかりと溶け込むことを大切にしました。掲示物やテントの形、スタッフの対応なども含めて、フェスに来ている方々と違和感のないコミュニケーションを取れるように心がけています。

フェス会場に自然に溶け込んでいるテント
寺井さん:従来のイベントのゴミ回収ステーションは、来場者がゴミ箱に直接捨てて、それをスタッフが支援・指導するという方法をとっています。でも、お客さんに対して「こっちじゃないです」と命令のようになってしまうこともあり、注意して行動を促す点がネガティブに感じていました。そうではなくて、笑顔でゴミを受け取って「私たちが分別しますよ」と伝えると、お客さんは手渡した後に「あ、ちゃんと分けてくれる方がいるんだ」と感謝が芽生える。『リソースハブ』はただのゴミ捨て場ではなくて、ポジティブな会話が生まれる場にしたいと思い、このような形になりました。

音楽フェス会場で最も多いのは飲食物のゴミ
資源だけじゃなく「ありがとう」の循環が生まれる場所。
一般の方にゴミの分別に参加してもらうとき、大事なことは何でしょうか。
寺井さん:ハード面とソフト面、その両方が揃っていることです。仮にゴミ箱が一つしかなかったら、来場者の方がどれだけ意識高く分別しようと思ってもできません。まずは、ゴミ箱の種類がきちんと揃っているハード面が重要です。
たしかに燃えるゴミの箱しかなければ、リサイクルできるはずの資源も一緒に捨てられてしまいます。
寺井さん:そしてもう一つ、意外と重要なのがソフト面です。ゴミ箱の種類だけが整っていても、そこに興味を引きつけて、行動を起こしてもらえるようなきっかけがなければ、人はなかなか行動しません。従来のイベントではソフト面の呼びかけが少なく、結果的にゴミが分別されていないことがありました。でも今回は、スタッフが丁寧に声かけをするなど、ソフト面がしっかりと機能している。僕らがいろいろな音楽フェスに関わってきた中でも、『リソースハブ』の最も重要な点はこれだと感じています。

「こちらでゴミの分別やっています!」と明るく親しみやすい声かけが印象的
実際に当日運営してみて、どのような気づきがあったのでしょうか。
寺井さん:皆さん「ありがとう」と言いながらゴミを渡してくれるんですよ。普通のフェスだと「あっちに捨ててください」とスタッフが命令するから、お客様もちょっと不機嫌になって帰っていく。でも、ゴミの受け渡しで「ありがとう」「助かったよ」の気持ちが生まれるから、柔らかくて温かい場になったと感じます。
白川さん:「ありがとう」の言葉が一日でこんなに聞けるんだ、と思うくらい。やっていてよかったなと感じました。
寺井さん:来場者の方がゴミを分別しているスタッフを見て「あ、ごめんなさい、全部まとめて持ってきちゃいました」と言っている場面もありました。きちんと分別すれば資源化できることを多くの人に知ってもらう意味でも、今回の受け渡しの方法は良かったのではないかと感じています。

ボランティアのスタッフは大学生や新社会人で、遠方から参加している人もいる
『GREEN×EXPO 2027』に向けて横浜市とも連携していく中で、ロスフラワー(検品基準を満たさず廃棄されてしまう花)のポット苗をプレゼントする企画も生まれました。
白川さん:ご提供いただいた苗が意外と大きかったので、なかなか持ち帰っていただけないのではないかと思っていましたが、スタッフが「お花を配っています」と話すと喜ばれて、開催2日目の時点でかなりの数をお持ち帰りいただきました。

お渡し時にロスフラワーの説明をしたり、チラシを配布したりといった工夫も

生花店やホテルなどから出る、花の廃棄量を削減できる
他にも会場内では、工事によって廃材となった学校体育館の床材をアップサイクルしたテーブルが設置されるほか、海洋プラスチックやロスフラワーの再利用、ペットボトルの水平リサイクルを推進する『ボトルtoボトル』といった取り組みも行われています。

小中学校の体育館のフロアがテーブルに

子どもたちが集めた海洋プラスチックは手作りキーホルダーの材料に
© 2025 Peanuts Worldwide LLC

ソニー・ミュージックエンタテインメントのRebloom Flower Projectでは、ライブ会場に贈られた祝い花を再活用してオリジナルポプリを作れるワークショップを開催
横浜から世界へ、人にも地球にもやさしいフェスを響かせよう!

お客様の「ありがとう」がスタッフのモチベーションにもなる
寺井さん:「臭いものに蓋」という言葉があるように、ゴミ箱の先がどうなっているのかは、情報としても届きにくい気がします。でも、オープンに発信していくほうが感謝の思いが生まれやすいし、「自分も協力しよう」という気持ちになるのではないかと改めて感じました。
白川さん:ゴミを捨てる、という行為がポジティブな体験に変わっていく。フェスの場はそのインフラになり得るのではないかと実感しています。まさにハブとして資源が循環し、さらなる交流が生まれる場を目指して、今後できることはまだまだたくさんあると思っています。
音楽フェスで出たゴミが、ちょっとした分別というアクションで、未来につながる資源へと変わる。『リソースハブ』の体験は、私たち一人ひとりの小さな行動が、持続可能な社会の実現に貢献できるという大切な気づきを与えてくれます。
『CENTRAL』をきっかけに、音楽フェスという特別な場だけではなく、日々の暮らしの中でも資源を大切にする意識が広がっていく。今まで何気なく捨てていたものを意識して分別するとき、きっと未来の地球からの「ありがとう」を受け取っているはずです。
【情報】
CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025
https://central-fest.com/
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
https://www.sme.co.jp/
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
https://www.sonymusicsolutions.co.jp/
株式会社博展
https://www.hakuten.co.jp/